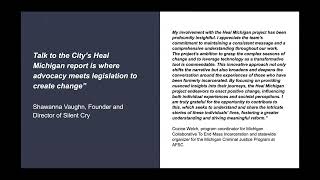初探Polis 2.0
初探Polis 2.0:シードレビューネットワークへ
2023年8月22日
Polis 2.0の初期探査:シードレビューネットワークへの移行。この記事では、Polisの運用方法、およびAOIが開発した群衆対話ツール「Talk to the City」との連携後のPolis 2.0の試行プロジェクトについて紹介します。さらに、将来のフィードバックネットワークとロールプレイングについてのブレインストーミングも行いました。
An Initial Exploration of Polis 2.0: Moving Towards Seed Review Networks。本文介紹了 Polis 的運作方法,與加入了 AOI 開發的群眾對話工具 Talk to the city 之後的 Polis 2.0 試行專案點子松 AI 民主化對齊大會。並就可能的回饋網絡與角色扮演的未來,進行腦力激盪。
Talk to the CityとPolis 2.0
Polis 1.0: 意見を集約する都市国家
Polisはオープンソースの群衆意見集約システムで、その名前は「都市国家」の意味から取られ、ネットワーク上で誰の意見も公平に扱われることを象徴しています。Polisは世界中で公民審議プロセスに広く応用され、オンラインとオフラインを統合する場面で特に有用です。Polisは参加型予算、法律改正、審議民主主義と密接に関連しており、大量の人々の本音を収集・分析し、彼ら自身の言葉で表現するために統計と機械学習を用いています。
Talk to the City 視覺化推特有關 AI 的星叢
Polis 1.0 匯集意見的城邦
Polis 是一個開源的群眾意見匯集系統,取其「城邦」原意,象徵在網路世界,人人的意見都可以被友善的、並陳的對待。因此 polis 被廣泛應用於世界各地的公民審議過程,尤其是需要線上與線下整合的環節。Polis 背後與參與式預算、法令修改、審議式民主息息相關。根據其官網所示,Polis 用於收集、分析和理解大量人們的真實想法,並以他們自己的言語表達,透過統計和機器學習來達成。
Polisの具体的なフロー
誰でもPolisアンケートを開始でき、準備が整った重要な声明(Seed Statement)を用意すれば、公開して回答を募ることができます。回答者は質問に答える過程で、次第に立場が近い陣営に分類され、その後グラフで視覚化されます。これにより、実際の審議プロセスで参加者が自分の立場をより明確に把握し、重要な声明に基づいてより効果的な議論が行えるようになります。
簡要敘述流程,任何人都可以發起一個 polis 問卷調查,準備好關鍵陳述(Seed Statement),便可以開放大眾前往作答。如同心理測驗的是非題選項,作答者在答題的過程中,會漸漸被劃分到立場相近的陣營,這樣的陣營在稍後會被視覺化,以圖表的方式顯現。這有助於之後實際的審議過程,讓參與者們更清楚自己的立場,並根據關鍵陳述,進行更有效的討論。
以上是 Polis 的具體流程,在台灣曾被應用於 vTaiwan(數位經濟法規線上諮詢)、READr 互動式報導頁面(如數位身分證、四大公投立場等報導)、台美議題互動等等,由於是開源工具,所有人都可以使用其工具。
Polis 2.0と都市対話
CIPとPolis 2.0
2023年4月、英国の非営利組織CIPは、OpenAIやAnthropicと共に大型言語モデル(LLM)開発に伴う対立問題について議論する「対話会議」を発起しました。デジタル庁(moda)は今年7月にアイデアソンでこれを試行し、Polis 2.0として知られるプロジェクトを実施しました。
Polis 2.0では、対話の対象を仮想人物(LLM)に広げ、全員が対話に参加できるようにしました。これにより、異なる見解を開示し、より多くの人々が対話を続けることができるようになりました。
Polis 2.0 與城市對話
今年四月開始,英國的非營利組織集體智慧專案(CIP)發起對齊大會(Alignment Assemblies, AA),與發行ChatGPT的組織OpenAI、發行Claude的公司Anthropic一起討論大型語言模型(LLM)開發時必然面對的對齊問題(Alignment Problem)。數位部(moda)作為夥伴,於今年七月於點子松(Ideathon)進行先行示範,也就是俗稱的 polis2.0。
如果說 polis 既有的威力,在於將不同時間的參與者進行齊一編列的記述(chronicle),以對齊彼此的歧見。那 polis 2.0 的特色在於,攤開歧見,讓所有人都可以繼續對話,而對話的對象為虛擬人大型語言模型(簡稱 LLM)(目前使用 ChatGPT, GPT3.5turbo)。
Talk to the Cityの役割
「Talk to the City」は、TwitterのツイートやPolisの結果など、異なるソースのクラスターをトレーニングして視覚化マップを作成するAOIのツールです。今回のアイデアソンでは、Polisの陳述意見と投票結果を「Talk to the City」に取り込み、新たな議題クラスターを生成しました。
這次在點子松頁面,除了可以看到數十項關鍵陳述的 polis 小卡可以作答外,AA 的過程也導入了「我城對談」(Talk to the City,暫譯)。「我城」為「人工智慧目標機構」(AI Objectives Institute, AOI)開發的工具,可以根據不同來源的叢集,如 Twitter 的推文、審議工作坊的立場、Polis 的結果,訓練出議題視覺化地圖。其中最創新的發明為,使用者可以與這些叢集繼續聊天。
LLM 會根據這些叢集的立場與你分享所見所聞。
這一次在台灣嘗試的對齊大會,便是將點子松的陳述意見與投票結果,餵進「我城」,並展開新的議題叢集,讓更多人可以與各個叢集繼續聊天,打開與不同異見對話的空間。
比如說,我點進「人工智慧倫理」的叢集,有一題是「法官在評估過程中不應使用AI工具。」,我接著回答「我不同意」,
帶有🏛️ 表情符號的 LLM 就會像沙包一樣回答「我理解你可能對這個問題有不同的看法。然而,我認為法官在評估過程中不應依賴人工智慧工具。人工智慧工具可能引入偏見或錯誤,影響判斷的公正性和準確性。人類的判斷能力,包括考慮背景、細微差別和主觀因素的能力,在評估複雜和主觀問題時是必不可少的。僅僅依賴人工智慧工具可能會損害評估過程的完整性。」
以上整體流程,被稱為 Polis 2.0。
Meta-polisとフィードバックループ
この試行は、デジタル公共領域のRPGゲームのようなもので、仮想人物と共に重要な議題を討論し、対立を調整する場を提供します。これにより、フィードバックネットワークが形成され、集団意見の擬人化が促進されます。
まとめ:関鍵評論ネットワークへの道
Polisは意見のテキスト化問題を解決し、大量の文字意見を収集するためのボトルネックを克服します。一方、Talk to the Cityはフィードバックの必要性を満たし、シード意見を自動的に生成します。この二つのツールの組み合わせにより、多様な意見リーダーの可能性が開かれ、「関鍵評論ネットワーク」が形成されます。
"Engineer's way of creating knowledge" the English version of my book is now available on [Engineer's way of creating knowledge]

(C)NISHIO Hirokazu / Converted from [Scrapbox] at [Edit]