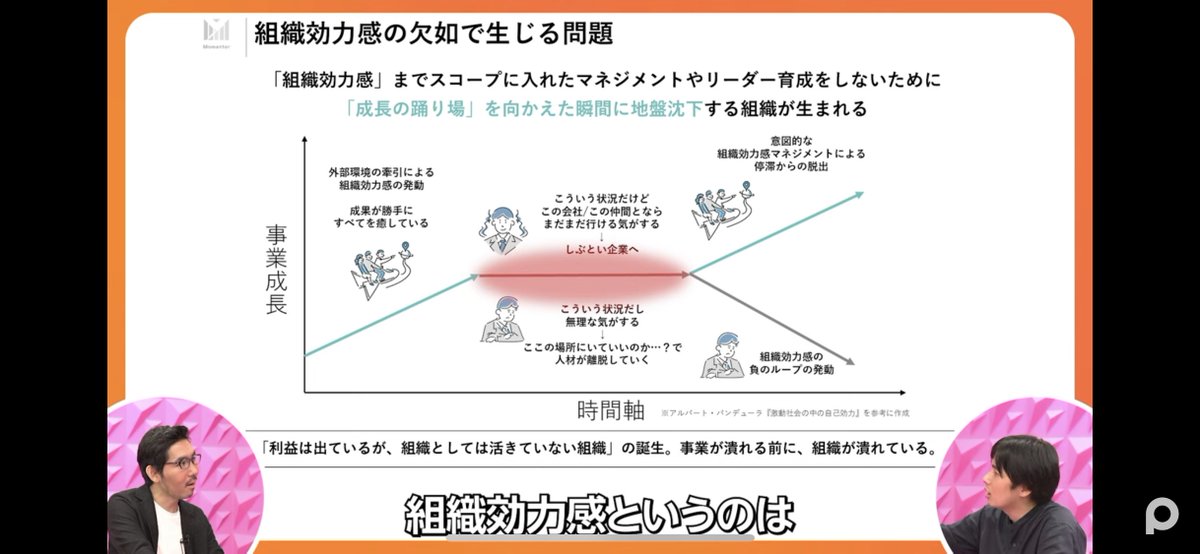主観的なコミュニティが重なり合っている
prev 社会は二つある
1: こんな感じの人のあつまりがある
Aさんは「みんなコミュニティのなかま!」と思ってる
Bさんは「A, B, Cが常連コアメンバーで残りはゲスト」と捉えている
Cさんは「Fさんも仲間でしょ」と思ってる
Dさんは自分も「A, B, Cと同様の常連コアメンバー」と思ってる(がBもCもそうは思ってない)
Eさんは「一度イベントに参加しただけであって、コミュニティに所属してるわけではない」と思ってる
Fさんは「友達のCさんと一緒にイベントに参加しただけで、Aさんのコミュニティに参加したわけではない」と思ってる
2: このような個々人で異なる多種多様なコミュニティ所属感が重なり合って「なんとなく色濃い、境界の曖昧なグループ」ができている
「社会は二つある」の「コミュニティは客観的には存在しない」は「コミュニティが客観的に存在するのではなく、それぞれの人々が主観的にコミュニティだと思ってるものがあって、それが重なり合って境界の曖昧なグループができている」と噛み砕けば同意できるのでは?
それぞれは個々人の信念
正統的参加というやつ
"Engineer's way of creating knowledge" the English version of my book is now available on [Engineer's way of creating knowledge]

(C)NISHIO Hirokazu / Converted from [Scrapbox] at [Edit]