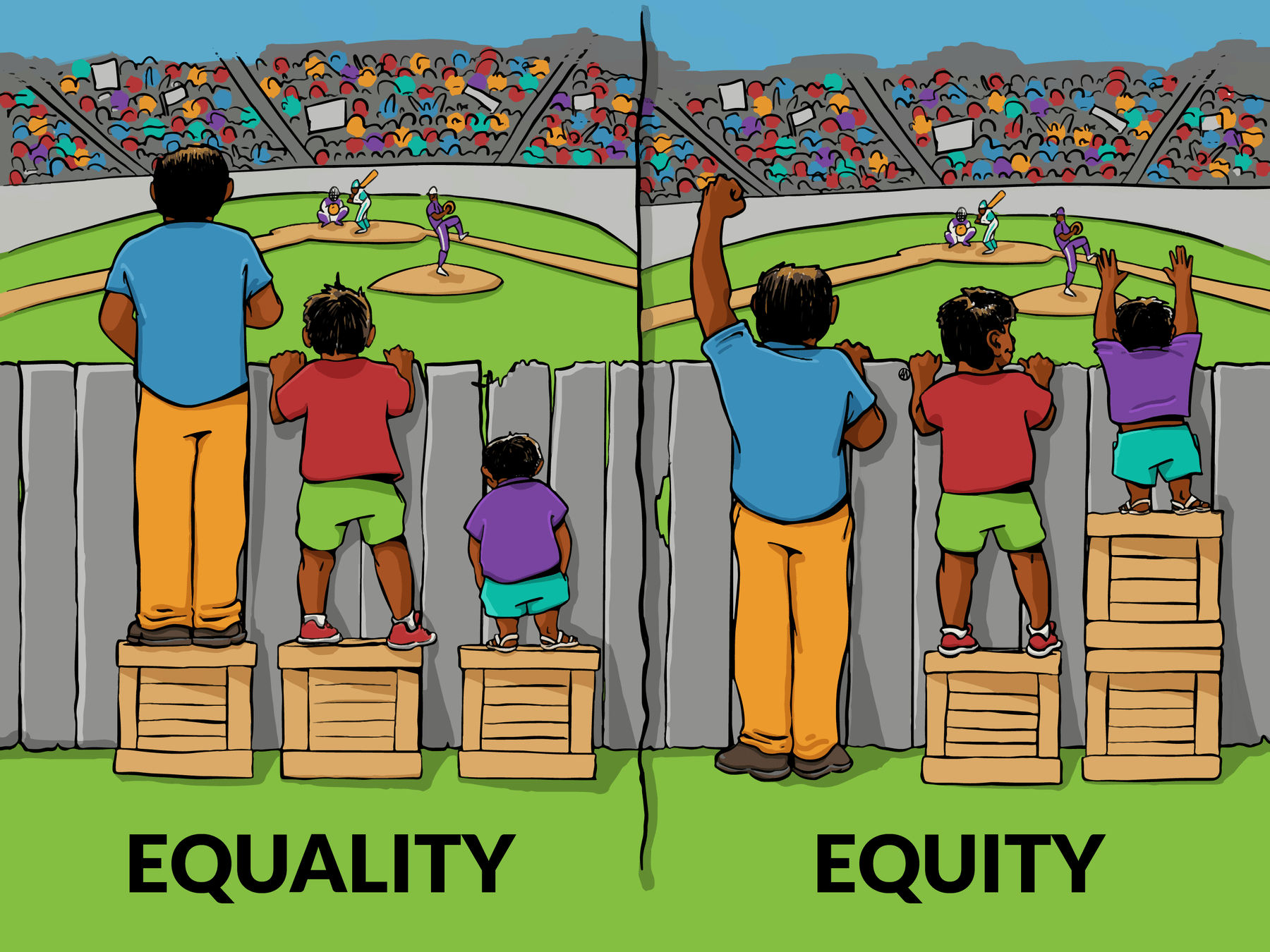文化による平和の違い
>brighthelmer 先日、「ウクライナに平和を」という話を聞いて思い出したのが、石田雄『平和の政治学』(岩波新書、1968年)掲載のこの図(p.35)。一口に平和といっても文化圏によってそのニュアンスは大きく違うという話。この表で左に行くほど正義が実現された状態を「平和」とする発想になるのに対して、
>brighthelmer 右に行くほど秩序や静穏を「平和」とする発想になるという。左側の「平和」は、正義の実現のためには積極的行動が必要とされるため、「平和のための戦争」にも接近しうる。他方、右側の「平和」は武力衝突のない状態を平和とするため、不正義をも見過ごすことになりうる。
>brighthelmer また、波風を立てないことが「平和」だと認識される社会では、社会全体が戦争に接近していくような状況下においては戦争に反対すること(=波風を立てること)がかえって難しくなるとも石田先生は指摘している。
>brighthelmer 一口に「平和」といっても、いろいろな解釈があり、それが何を意味しているのかをきちんと考えないと何も言っていないのと同じだということだろう。なお、石田先生の「平和」概念分析は『日本の政治と言葉(下)』(東京大学出版会、1989年)でも行われている。終
"Engineer's way of creating knowledge" the English version of my book is now available on [Engineer's way of creating knowledge]

(C)NISHIO Hirokazu / Converted from [Scrapbox] at [Edit]