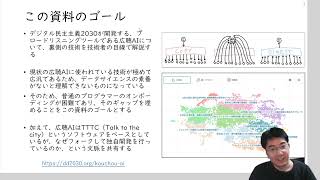Talk to the Cityと広聴AIの仕組み
某原稿から有用なので切り出してシェア
Talk to the Cityや広聴AIがどういう仕組みで動いているのかを簡単に説明します。
まず人々の発言などの自然言語データからLLMによって細粒度の表現を抽出します。
データは文字列のリストであればなんでもかまいません。
過去の事例では、X(Twitter)などのSNSからAPIで特定のキーワードを含むものを抽出したり、Google Formでお題に対する意見を集めたり、Google Mapの特定地域範囲に書かれたレビューを収集したり、Steamでゲームにつけられたコメントを集めたりなどが行われてきました。
「細粒度の表現」として何を抽出するのかはLLMに対するプロンプトで制御され、ユースケースに応じて変えることができます。
たとえば「意見」を抽出することができます。
他には「質問」や「批判」や「問題意識」などを抽出することもできます。
ユーザの投稿の中には複数の意見が含まれることもあれば、意見が含まれないこともあります。
個の抽出フェーズの処理によって、多様なユーザ投稿から、粒度の揃った分析対象の集合を作ります。
Talk to the City以前はこの抽出される細粒度表現が「キーワード」や「トピック」でした。
つまり、単語や数単語のフレーズだったわけです。
Talk to the Cityでは短文を抽出します。
このことによってよりよく意味を保持できるようになりました。
抽出ステップの次のステップでは、LLMを用いて短文を数千次元の高次元空間に埋め込みます。
2013年に登場したword2vecに始まるこの技術は、2020年代に入ってからBERTやGPTの登場で大きく進歩しました。
この埋め込みベクトルは、意味的に似ている短文が近くに配置されるように設計されています。
この埋め込みベクトルを使うことで、意味的に似ている短文を数学的に近いものとして扱うことができるようになりました。
これが可能になったことで、前段での抽出ステップで抽出される細粒度の表現としてキーワードではなく短文を抽出することが有用になったのです。
このステップ以降には多様なバリエーションがあります。
たとえば2018年に発明された時限削減手法のUMAPを使って数千次元のベクトル分布を2次元に次元削減し、散布図として可視化することができます。
高次元または低次元のベクトルに対してクラスタリングをかけて「似た意味の意見」のグループを作ることができます。
クラスタリングで作られたグループのなかにどのような意見があるのかを、LLMに読ませて解説を生成することができます。
広聴AIの特徴は、このクラスタリング部分で階層的クラスタリングを使うことです。
たとえば8000件のデータを20件のざっくりとしたグループにとして観察可能にし、興味を持ったものさらに20件の細かいグループに分けて深掘り観察する、という使い方ができます。
技術的には、最初にk平均法で400件のクラスターを作り、次に各クラスターに対して階層的クラスタリングをかけて20件まで凝集させる、という2段階のクラスタリングを行っています。
拙著『エンジニアの知的生産術』でも解説しましたが、このようにまずは大雑把に全体を俯瞰し、興味を持った部分を深掘りしていくスタイルは、知的生産において非常に有効です。
従来はこのような階層的な目次は人間が手作業で作る必要がありました。
大勢の人が口々に色々なことを言っているデータに対して、人間が整理をするのはとても大変です。
広聴AIのような技術によって、AIが階層的な目次を自動生成し、人間の知的生産を支援することが可能になりました。
広聴AIのもう一つの特徴は「濃い意見グループ」に注目する機能です。
これはベクトル空間上での点密度を用いて注目するクラスタを選ぶ機能です。
たとえば8000件のデータが400件のクラスタに分けられたとき、400件のクラスタの1つは平均的に全データの0.25%にあたる20件のデータを含むことになります。
これは今までは1%未満の少数意見として切り捨てられがちでした。
しかし、この20件のデータが例えば異なる人の異なる要求をする文章から抽出された類似の問題意識だった場合、これは重要な発見につながる可能性があります。
つまりこれは「予期しないつながり」の発見支援なのです。
もちろん、同一人物による繰り返し投稿や近しい人間による組織的投稿でも密度は高くなるのでこの尺度だけで重要性を判断することはできません。
将来的には、投稿者の多様性なども考慮に入れたスコアリングへと発展するでしょう。
Related Pages
- →dd2030×デジタル民主主義×広聴AI×大規模熟議支援システム『いどばた』×安野たかひろ×チームみらい×安野貴博氏に聞く!デジタル民主主義×平デジタル大臣、安野さんについて語る×デジタル民主主義2030×digital_democracy_2030→

- →安野_貴博×鈴木_健×東_浩紀×プルラリティ×ゲンロン250626×ised×デジタル民主主義2030×アメリカ大統領選2024ロードトリップ×ハンナ・アーレント×革命について×革命×自由の創設×タウン・ミーティング×評議会×natality×政府効率化省×doge×なめらかな社会とその敵×21世紀のイデオロギー×差異があるという意味において平等×協力の深さと広さのトレードオフ×pluralityとハイプカーブ×ハイプカーブ×community_notes×pol.is×pol.isでのuberの議論×quadratic_voting×quadratic_funding×Talk to the City×ブロードリスニングが国会で野党が総理大臣に質問するために使われた事例×ハーバーガー税×joi_ito×創発民主制×weblog×草の根の民主主義×emergent_democracy×伊藤穣一×ブログ×rss×双方向メディア×下からの自己組織化×歴史は循環する、しかし内容はより高次のものとなる×似た物が昔にもあった型思考×テクノ封建制×civilization×東京大学pluralityセミナー2025-05-12×統合テクノクラシー×企業リバタリアニズム×デジタル民主主義×ブロードリスニングが1年で標準戦略に×ひまわり学生運動×radicalxchange×why_i_am_not_a_market_radical×plurality(2022)×pluralityは無色の新語として作られた×tokyo_plurality_week_2025×d/acc×マルクス主義×加速主義×柄谷行人×世界史の構造×マルクスその可能性の中心×探究_ⅰ×誤配×ルクレティウス×ずれ×すべてのものには裂け目がある。そこから光が差し込む×違いを越えて協働するための技術×一般意志×全体主義×単一性×エロイーズ×訂正可能性×垂直的×単一的×カール・シュミット×カール・シュミットの「議会批判」と「独裁」論×コネクテッド・ソサイエティ×ダニエル・アレン×規範的plurality×アジェンダ設定の権限を人々に開放する×請願権×オンライン請願×james_s._fishkin×詐欺犯罪危害防制條例×mini-public×いどばた政策×stanford_online_deliberation_platform×forkability×正統性×自己主権型アイデンティティ×伊藤_孝行×安野チーム台湾報告会×audrey+glen+colin+pmt研究会×【オードリータン✖️小川淳也】未来を共創するデジタル民主主義×玉木雄一郎+Plurality×愚行権×audrey+tbs_cross_dig×裏ハイデガーとしてのアーレント×今北勢問題×訂正可能性の哲学×家族性×家族×動的な認知的膜×ホロン×クリプキのクワス算×truth_social×政治家は猫になる×社会資本が王である世界×アテンションエコノミー×贈与経済×台湾の同性婚は親族にならない×2ステップの熟議×アーレントのwork×ファンダム→
- →選挙は4年に一度5bit送信する遅い通信だ×デジタルネイティブは4年に1度のアップロード帯域で十分とは思わない×if文から機械学習への道×どんどん複雑な条件分岐になっていく×cultural_preferences_for_formal_versus_intuitive_reasoning×教師あり学習×ロジスティック回帰×決定木×家族的類似性×東洋人はロジスティック回帰で西洋人は決定木×ルールベースパラダイムが重み付き和パラダイムに負けたエポック×vibe_coding×一部が消えて一部残り新しく生まれる×captcha×人間でないユーザ×認知戦×輿論戦×法は社会のos×九電玄海原発、ドローン侵入か×ウクライナ向け「ストライクキット」3.3万台供給×共有地の悲劇×ossで共有地の悲劇が起こることにどう対処するか×大きな政府と小さな政府×「大きな政府/小さな政府」は誤った二項対立×オストロム×公共財×共有資源×cpr×common-pool_resource×connections_between_indivisuals_as_first-class_objects×intersecting_group×新しいものは登場前にその価値を見積もることができない×ブロードリスニング×ai_objectives_institute×Talk to the City×デジタル民主主義2030×広聴AI×ブロードリスニングが国会で野党が総理大臣に質問するために使われた事例×日本維新の会のブロードリスニング事例×polis×既存のsnsは個人に注目させるが、polisは個人ではなく集団に注目させる×citizens_foundation×your_priorities×リプライさせない仕組み×別席調停×左派がよい主張をしているなら、右派がやるべきことは同じくらいよい主張であり、戦うことではありません×いどばたシステム×bitcoinはお金、ethereumはコンピュータ×中央集権の3つの軸×polymarket×1人1票×quadratic_voting×quadratic_funding×vitalik_buterin×gitcoin_grants×retroactive_public_goods_funding×futarchy×an_introduction_to_futarchy×幅がある→
- →インターネットと電気があり焚き火ができる施設×aiチャットログから有用な情報だけ保存×自然人村(東京・あきる野市)×青野原_野呂ロッジキャンプ場×プロジェクト個別ログページからプロジェクトページにリンクする×プロジェクトの片付け×政策プルリク活用プロジェクト×dd2030_slack×広聴AI×インタビューaiグランプリ2025-12-02×2025年のブロードリスニング×code_for_japan_summit_2025×p-mem/vt2025-11-22×脱線×日記2025-12-01×日記2025-12-03×日記2025-08-24×日記2024-12-02→
- →インタビューaiグランプリ×広聴AI×チームみらい2025参院選「しゃべれるマニフェスト」オープンデータ×チームみらいの社会実験「しゃべれるマニフェスト」から得られた知見×しゃべれるマニフェスト×チームみらいクラスタ密度ソート×チームみらい階層的クラスタリング×星さんのprでの議論のpolis×colin_megill×チームみらい問題意識の広聴ai×いどばた政策→
- →11/18(火)×2024年振り返り×世論地図2024振り返り×世論地図×Talk to the City×ブロードリスニング×しゃべれるマニフェスト×チームみらい2025参院選「しゃべれるマニフェスト」オープンデータ×チームみらいの社会実験「しゃべれるマニフェスト」から得られた知見×devinを見る会×scott_wu来日×devin使ってみてどうだった?_~活用事例と導入時のポイント~×llmを使いこなすエンジニアの知的生産術(講演資料)×未踏ジュニア×一般社団法人未踏の理事を退任しました×広聴AI×jigsaw_sensemaker×tttc勉強会×advanced_voice×aipm2025-03-11×日記2025-04-05→
- →Talk to the City試す×polis×意見のクラスタリング×Talk to the City×トピックのクラスタリング×Talk to the Cityのクラスタリング×bertopic×countvectorizer×著作権法30条の4×著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用×センチメント→
- →主観か客観かではなく、一人の主観から大勢の主観へ×ブロードリスニング×情報の複製により情報発信は効率化されたが、受信は改善しない、情報を減らす技術が必要×要約技術×関_治之×シビックテックによる、社会と民主主義のアップデート×polis×Talk to the City×andrew_trask×一人の人間が何百万人と対話することが可能になる×広範囲の傾聴×広聴×多聞×広範な傾聴×デジタル広聴×安野たかひろ氏が東京都知事選に出馬へ×glen_weyl×知的生産性×生身の人間×人間増強×plurality×broad_listening×deliberation×熟議×polisをもっとやりたい×多重視点×生煮えのトピック×切り口→
- →サイボウズラボ勉強会×jigsaw_sensemaker×tttc勉強会×jigsaw_sensemaker×ボーリンググリーン×星さんのprでの議論のpolis×polis型データ×talk_to_the_city_turbo×tttc-light-js×whose_opinions_do_language_models_reflect?×プロンプトはllmに作らせるほうがいい×チャットから知見を引き出すシステム×talk_to_the_city_scatter×plurality本の概念マップ×どこから来たのかのトレーサビリティ×しゃべれるマニフェスト×いどばたビジョン×cartographer×トップダウンの分類×aiでkj法2024-12-19×kj法×かならず小分けから大分けに進まなければならない×発想法×周辺的な主張×取りこぼし×ごちゃごちゃした少数意見は捨てたほうがいい×オフトピック×わかりやすいレポート作成×創発的なプロセス×既存の枠×霞ヶ関のポンチ絵×みんなの意見を聞いてます感の演出×文書作成過程で生成された不用知の収集と活用可能性の検証×境界をまたぐ×既存のグループを跨ぐ関係性×kj法勉強会振り返り勉強会×sensemaker×広聴AI×kozaneba×psensemaker2025-10-17×psensemaker2025-10-21×高次元空間でクラスタリングしてからumap×クラスタ解説の埋め込みベクトルをconcatしてUMAP→
- →Jigsaw Sensemakerとtttc-light-js勉強会×分布を観察して気づくこと×d-agreeシステム×common_ground×uncommon_ground×意見の相違点×分断の可視化×polis型データ×ブロードリスニングの4つのデータ型×突きつけるブロードリスニング×ブロードリスニングが国会で野党が総理大臣に質問するために使われた事例×みらいaiインタビュー×cartographer×いどばたビジョン×Cartographerやfarbrainが改善するもの×farbrain×広聴AI×farbrainは広聴aiのリアルタイム化×協力の深さと広さのトレードオフ2025-11-01×広く集めたいのか多様な意見を集めたいのか→
- →広聴AI×抽出された知見×大量のオブジェクト×主観的興味深さ×今持っている知識の一歩先の知識しか受け止められない×ガウス過程回帰×利用と探索のトレードオフ×興味深さ×主観×cartographer×多様性ペナルティ×maximal_marginal_relevance×upper_confidence_bound×random_kitchen_sinks→
- →dd2030_slack×広聴AI×既知のものの除去を人間がやるべきではない×既存の概念とぶつける×既存のカテゴリーの隙間に落ちてるボール×年老いた組織×もう知ってる×組織を変えるオペレーション×認知コストの削減×自分の知識の境界をaiにインプットする必要がある→
- →polis型×投票行列×vote_matrix×ボーリンググリーン×インタビュー型×デジタル民主主義2030×いどばたシステム×しゃべれるマニフェスト×チームみらいの社会実験「しゃべれるマニフェスト」から得られた知見×多数決×多数決を疑う×量的研究×質的研究×単語頻度分析×トピック抽出×Talk to the City×polis型データ×2022年参院選のpolis的可視化×オープンクエスチョンは答えにくい×一つのテキスト欄に過不足なく意見を整理して書くことが難しい×いどばたビジョン×みらいaiインタビュー×文法的クローズドクエスチョンを概念的に開く→
- →意見のトレーサビリティ×広聴AI×両方向のトレーサビリティが必要×どこから来たのかのトレーサビリティ×どこへ行ったのかのトレーサビリティ×トレーサビリティ×双方向トレーサビリティ×双方向参照関係×意見の反映経路×寄与の可視化×根拠と接続→
- →日記2025-10-02×もっとインサイトが取れる仕組み×広聴AI×いどばたシステム×自由記述のアンケート×文脈欠落×「n=1の意見を深掘りしたい」は「速い馬が欲しい」×ミミズとショートケーキのたとえ×羊のたとえ×新しく作る人×変革する人×壊す人×シリアルアントレプレナー×存続することが目的化する×機能しなくなったものは破棄しなければならない×現状維持バイアス→
- →サイボウズラボ勉強会×ブロードリスニングの「あの図」勉強会×ブロードリスニング×都知事選2024×Talk to the City×日テレnews×2024衆院選×ブロードリスニング×世論地図×plurality和訳×japan_choice×議員pedia×投票ナビ×政治参加×社会参加×じぶんごと×可視化×11万人の意見クラスター分析×polis×aiによるクラスタ解説×mielka×結城_東輝×台湾デジタル発展省×mashbean×funding_the_commons_tokyo_2024×glen_weyl×glen+japanchoice×plurality×大きな物語×polis体験レポート:同性婚を合法化すべきか×polis勉強会×polis:_scaling_deliberation_by_mapping_high_dimensional_opinion_spaces×主成分分析×シルエット係数×fisherの正確確率検定×convex_hull×d3.js×モバイルファースト×majority_judgement×多数決×polis_2.0×AIクラスタ解説×会社さんはいない×2022年参院選のpolis的可視化×東京大学谷口研究室・朝日新聞社共同調査×公明正大→
- →funding_the_commons_tokyo_2024×plurality_in_japan×ftctokyo!×ftctokyo×Talk to the City×audrey_tang×glen_weyl×plurality:_technology_for_collaborative_diversity_and_democracy×チームワークあふれる社会を創る×理想への共感×100人100通りの働き方×100人100通りの人事制度×デジタルツール×多様性×funding_the_commons×柄谷行人×交換様式論×デジタル民主主義×交換様式a×colors.js事件×beyond_public_and_private×安宅_和人×intersecting_group×21世紀のイデオロギー×統合テクノクラシー×企業リバタリアニズム×ブロードリスニング×主観か客観かではなく、一人の主観から大勢の主観へ×vtaiwan×polis×メディアとしてのグループウェア×生産性向上ソフトウェア×ソーシャルメディア×一丸となって共通の目標を達成×変化に適応×プロソーシャルメディア×グループウェア×副業×複業×パラレルワーク×理解され、実行されるまでの時間を短縮する×アジェンダ設定の権限×参加型政策立案×参加型予算編成×majority_judgement×quadratic_voting×kj法の累積的効果×vtaiwanでuberに関する議論がどう進展したか×Meetup with Audrey & Glen×audrey+glen+halsk@cybozu×未来はすでにまだらに存在している×組織の境界×なめらか化×開門造車、你行你来×思惟経済説×plurality質疑@ftctokyo→
- →plurality_tokyo_namerakaigi×サイボウズラボ勉強会×pol.is×community_notes×メカニズムデザイン勉強会×majority_judgement勉強会×pluralityとpolis勉強会×polis勉強会×quadratic_votingとplural_management勉強会×Talk to the City勉強会×世論地図勉強会×高次元データ分析勉強会×デジタル民主主義研究ユニット×ピボット×古典期アテネの民主主義のスケール×国民こそが唯一の正統な権威である×フランス革命×フランスでの女性参政権×一人一票×未成年者には投票権がない×成年被後見人の選挙権×ドメイン投票方式×デメニー投票×デーメニ投票×quadratic_voting×glen_weyl×qv×radical_markets×audrey_tang×vitalik_buterin×quadratic_funding×audrey_tangのqv×glen_weylのqv×quadratic_votingがシナジーの発見に有用×台湾総統杯ハッカソン×qvは投票しないことに意味のあるメカニズム×「投票しないことは良くないことだ」は根拠のない思い込み×vitalik_buterinらのquadratic_funding×a_flexible_design_for_funding_public_goods×akb48総選挙×gitcoin×gitcoin_grants×公共財×リソースの再分配×社会的意思決定×メカニズムデザイン×多数決×くじ引き×抽選制×抽籤制×プラトン×アリストテレス×ジェームズ・マディソン×ジョン・スチュアート・ミル×アレクシ・ド・トクヴィル×選挙は4年に一度5bit送信する遅い通信だ×ブロードリスニング×polis×pol.isでのuberの議論×metaがファクトチェックを廃止×community_notesにおける行列分解を用いた信頼度スコアリング×多様な主体から支持されることを評価する仕組み×Talk to the City×日テレnews×2024衆院選×ブロードリスニング×シン東京2050ブロードリスニング×UMAP×世論地図×mielka×2024衆院選×japan_choice×meta-polisの構想×mashbean×協力の深さと広さのトレードオフ×plurality本×aiあんの×タウンミーティング×非同期化×空間と時間の制限から解き放つ×chatgptとaiあんののコミュニケーションの形の違い×ai政治家の3つのレベル×aiが間に入って非同期化×open_space_technology×アジェンダ設定の権限を人々に開放する×vitalik×主観主義×3つのイデオロギーの間に2つの対立軸がある×aiが仲介するコミュニケーション×bluemo×intersubjective_model_of_ai-mediated_communication:_augmenting_human-human_text_chat_through_llm-based_adaptive_agent_pair×時間の制約×心理的安全性×緩やかに繋ぐ×デジタル民主主義2030×同じ時間と場所を共有できない人に機会を用意×metapolis×スケーラビリティ×デジタル民主主義×コミュニティ×大規模コラボレーション×xy問題×熟議のための4つのステップ×リプライはスケールしない×リプライさせない×your_priorities×コトノハ→
- →ボイスチェンジャー×浮いてる葉っぱをすくってどける×ストレッチ×骨盤×中臀筋×内転筋×菱形筋×合宿×ラボ発表会7/16×選挙は期間限定のゼロサムゲーム×polimoneyに注釈機能をつける×広聴AI×散髪×luup×stfuawsc×japan_dashboard×左派がよい主張をしているなら、右派がやるべきことは同じくらいよい主張であり、戦うことではありません×死票リスク×日記2025-07-10×日記2025-07-12×日記2025-04-02×日記2024-07-11→

- →広聴AI×社会を人間による計算として考える:ドラフト×書いた方がいい記事×日記2025-07-04×pr活用を支える技術(資料)×thankyou-helper×ショート動画メーカー2×世界の成長から取り残されると困る人×デジタル大乗仏教×大乗仏教×雑な二分法×チームみらい×分断を減らす×ショート動画×日記2025-07-09×日記2025-07-11×日記2025-04-01×日記2024-07-10→
- →pluralityとサイボウズ(2023)×ブロードリスニング×都知事選2024×日テレnews×2024衆院選×ブロードリスニング×シン東京2050ブロードリスニング×デジタル民主主義2030×広聴AI×いどばたシステム×aiの進歩とplurality×plurality本発売×tokyo_plurality_week_2025×チームみらい×デジタル民主主義2030、新ボード体制のお知らせ×チームみらいのソフトウェア開発の4割はai×pluralityとは×singularityでいいのか?×効率と包摂のトレードオフ×100人100通りの働き方×サイボウズの自由すぎる働き方はこんなやり方で管理されていた×メディアとしてのグループウェア×anti-social_media×pro-social_media×政治的対立×polis×polis体験レポート:テロの原因究明をするか×kintone×みらいいどばた会議×デジタル民主主義×代表制民主主義×ヒエラルキー×ティール組織×組織統治メカニズム×ブロードリスニングが1年で標準戦略に×日記2025-07-16→
- →未踏ジュニア×plurality_tokyo_2023×ブロードリスニング×主観か客観かではなく、一人の主観から大勢の主観へ×激動の2024年5月下旬×TTTC: AIと著作権に関するパブリックコメント×funding_the_commons_tokyo_2024×ftc2024安野+audrey×plurality_in_japan×日テレnews×2024衆院選×ブロードリスニング×シン東京2050ブロードリスニング×デジタル民主主義2030×広聴AI×Talk to the City と広聴AIの歴史×ブロードリスニングが国会で野党が総理大臣に質問するために使われた事例×りっけんai井戸端会議×再生の道ブロードリスニング×ブロードリスニングが1年で標準戦略に×plurality本×協力の深さと広さのトレードオフ×偽情報×audreyとd/accとdifferential×民主主義は社会的技術×qarasu-14bに質問をする×reasoningモデル×無意識データ民主主義×未成年者には投票権がない×台湾のjoinで高校生の提案が制度改善につながった×親ソーシャルメディア×橋渡しする意見×ブリッジングボーナス×灘校土曜講座→
- →Talk to the City勉強会×ブロードリスニング×Talk to the City×TTTC: AIと著作権に関するパブリックコメント×Talk to the CityでPlurality本の内容を可視化×デジタル民主主義×デジタル投票×民主主義×投票×政治家×公職選挙法×参加型予算編成×参加型予算編成:東京の事例×plurality×audrey_tang×funding_the_commons_tokyo_2024×good_enough_ancestor→
- →安野チームに参加したきっかけ×未踏ジュニア×plurality_tokyo_2023×rickshinmi×安野_貴博×plurality本×関_治之×思考の結節点2024-05-23×都知事選xデジタル民主主義×Talk to the City×gisele_chou×tkgshn×talk_to_the_city_turbo×11万人の意見クラスター分析×japan_choice×talk_to_the_city_scatter×aiパブコメ×TTTC: AIと著作権に関するパブリックコメント×シビックテックによる、社会と民主主義のアップデート×ブロードリスニング×broad_listening_in_practice×ブロードリスニングの「あの図」×2024→
- →週記2025-04-15~2025-04-26×pnp×pbt×v-1グランプリ×bluemoさんにサイボウズでいどばたイベントをしてもらう企画×social_hack_day_#70×scott_wu_youtube_japan_2025-04-22×安野たかひろ参院選出馬検討×デジタル民主主義2030×広聴AI×tokoroten→
- →サイボウズラボ勉強会×デジタル民主主義2030×join×市民参加型の政策形成プロセス×Talk to the City×東京都ai戦略いどばた会議×azure_blob_storage×azure_container_app×oss_weekly_reporter×o1_pro×gpt-4.5→
- →aiと著作権に関するパブリックコメント×Talk to the City×ブロードリスニング×全体感を抽出×パブコメの可視化×シビックテックによる、社会と民主主義のアップデート×クラスタを掘り下げる×aipubcom→

- →dena_techcon_2025×なぜそれが成り立つのか×コーディングを支える技術×プログラミング言語の背後にある設計思想×単なるスキル習得を超えた知的好奇心×エンジニアの知的生産術×自己改善へのこだわり×devin×技術の最前線に触れようとする姿勢×デジタル民主主義×ブロードリスニング×東京都知事選×安野たかひろ×Talk to the City×技術を社会に還元したい×plurality×社会的インパクト×デジタル公共資産基金×オープンソースの哲学×技術が公共財として機能する×サイボウズ・ラボ×一般社団法人未踏×報酬がゼロでも複業をやる×新しい学びや挑戦を優先するマインド×チームワーク×生産性向上×組織文化への貢献×外部脳×2日連続の登山×身体的な挑戦×知識共有に積極的×透明性×コミュニティへの貢献×よい方向性×民主主義のスケーラビリティ×mitou2024_demo_day×次世代のクリエイター支援→
- →対立は恐れずに活用すべきエネルギー×airbox×相互運用性とスーパーモジュラリティ×quadratic_votingがシナジーの発見に有用×参加者が多いほど良いシグナルが得られる×地元発のプロジェクトを全国インフラ化する×多様な意見の橋渡しの価値が高い×joinでの賛成反対2カラム表示×署名した人にメールを送り、オンライン会合に来る人を募る×台湾の詐欺防止法におけるデジタル署名×help_the_helpers×10代の若者によるオンライン請願×trustlessではなくtrust-building×抗議とデモの違い×公共財×スーパーモジュラリティ×組み合わせによる相乗効果×vtaiwan×join.gov.tw×デモ×解決策の提示×二次投票×quadratic_voting×デジタル署名×did/vc×pol.is×Talk to the City×橋渡しボーナス×橋渡し×トラストレス×ブロードバンドは人権→

- →2022年参院選のumap可視化×pca×世論地図×東京大学谷口研究室・朝日新聞社共同調査×次元削減×Talk to the City×t-sne×bertopic:_neural_topic_modeling_with_a_class-based_tf-idf×bertopic→
- →望遠鏡×客観性×主観的解釈×取捨選択×要約×職人技×費用対効果×Talk to the City×要約職人×自動編み機×靴下職人×教会の権威失墜×科学の権威失墜×主観か客観かではなく、一人の主観から大勢の主観へ→
- →サイボウズ×ブロードリスニング×日テレnews×2024衆院選×ブロードリスニング×kintone×Talk to the City×openai_apiのrate_limit×TTTC:empty vocabulary×TTTCの「離れ小島クラスタ」問題×良い議論ができる場を可視化の後につける→
- →Talk to the City×TTTCをAzure OpenAIで使う×proj-broadlistening×blu3mo×TTTC:形態素解析×日テレnews×2024衆院選×ブロードリスニング×形態素解析→
- →polis×pca×Talk to the City×UMAP×tttc的クラスタ説明生成×地図×データの多いpolisは半分こになりがち×イデオロギー・ベクトルの可視化×11万人の意見クラスター分析→
- →人生の選択肢をどうやって知ったか?×aiにkj法を教える×Talk to the Cityを試したい×Talk to the City×kj法×kozaneba×Talk to the City勉強会→
- →樋口_恭介×bertopic×Talk to the City×安野たかひろ×polisからのエクスポート×日記2024-06-22×日記2024-06-24×日記2024-03-15×日記2023-06-23→

- →scrapbox×西尾泰和のscrapbox×scrapbox→cosense名称変更×西尾泰和のcosense×ポインター×ハンドル×誤った二者択一×第三の選択肢×西尾泰和の外部脳×外部脳×クローズドソース×プロプライエタリ×私の著作物をすべてcc-0にしたい×mem.nhiro.org×Talk to the City×フラクタル要約×西尾泰和の落書き×非言語的シンボル×落書き×scrapbox期×外部脳期×これは何?(~2024-09-08)×これは何?×2024-09-08外部脳github作業→
- →サイボウズラボユース夏合宿2024×open_space_technology×エストニア×台湾×チベット×山古志村×21世紀のイデオロギー×自由×効率×アルゴリズムによる最適化×aiによる統治×自由→力と格差×ossと小さな政府×熟議×polis×Talk to the City×ai_objectives_institute×stanford_online_deliberation_platform×ブロードリスニングとAIあんの×デジタル公共資本基金→
- →サイボウズ×plurality×funding_the_commons_tokyo×公共財としてのサイエンス×デジタル公共財×デジタル民主主義×オードリー・タン×グレン・ワイル×ブロードリスニング×多様な個性を重視する×異なる視点を持つ人々の協力×対話と議論×協力のための技術×シビックテック×code_for_japan×知的生産性×安野たかひろ×aiと人間の協調×統治形態×Talk to the City×aiによる統治×人間の意思決定×政治家は猫になる×22世紀の民主主義×21世紀のイデオロギー×broad_listening_in_practice×dig_dao×デジタル庁×web3.0×digdaoマッチングドネーション×quadratic_funding×代表制民主主義×市民参加×意思決定プロセス×納得感×社会的合意形成メカニズム×激動の2024年5月下旬×audrey+glen+halsk@cybozu×x_spaceの音声をダウンロードする→
- →polis2024年夏×デジタル民主主義×アジェンダ設定の権限を人々に開放する×Talk to the City×オープンデータ×polis準備:選挙ポスター×polis準備:_新しい民主主義×2024年夏polis祭り:インスタンスの準備×polis準備:自治体dxの情報システム共通化×polis準備:0歳投票権×polis準備:神宮外苑再開発→
- →aiと著作権に関するパブリックコメント×Talk to the City×Talk to the Cityのクラスタリング×都知事選xデジタル民主主義×talk_to_the_city_turbo×talk_to_the_city_reports×東京大学谷口研究室・朝日新聞社共同調査×ppolis2024-05-27×スモールスタート×Polisは意見のクラスタリング、TTTCはトピックのクラスタリング×Talk to the CityでPlurality本の内容を可視化→
- →tokyoai×高橋_直大×Talk to the City×安野たかひろ×東_浩紀×馬田_隆明×関_喜史×選挙活動dx×歴史の転換点×ひまわり学生運動×アラブの春×audrey_tang×大前提として劣化する×テクノロジーと民主主義の対立×良質な情報を持っていると予言の成功率が高まる×他人が価値を見出す前にポジションを取れ×デジタル民主主義×オモイカネ勉強会×日記2024-06-23×日記2024-06-25×日記2024-03-16×日記2023-06-24→

- →サイボウズラボ勉強会×plurality_tokyo×plurality×ブロードリスニング×polis×pluralityとpolis勉強会×polis勉強会×plurality_seoul×audrey_tang×gisele_chou×Talk to the City×ai_objectives_institute×deger_turan×aiと著作権に関するパブリックコメント×安野たかひろ氏が東京都知事選に出馬へ×マイナンバーカード×直接投票×オープンソース×デジタル公共財×人間増強×知的生産性の向上×都知事選でTalk to the Cityをする×tokyoai×主観か客観かではなく、一人の主観から大勢の主観へ×シビックテックによる、社会と民主主義のアップデート×手書きの図×polis:_scaling_deliberation_by_mapping_high_dimensional_opinion_spaces×polis体験レポート:同性婚を合法化すべきか×台湾の同性婚は親族にならない×vtaiwan×オープンガバメント×デジタル民主主義×透明性×参加型民主主義×アジェンダ設定の権限を人々に開放する×モデレーション×polisのモデレーション×AOIのTTTCページにAudrey Tangのコメントがある×集団的議論×集団的意思決定×peter_eckersley×electronic_frontier_foundation×let's_encrypt×certbot×privacy_badger×brittney_gallagher×Talk to the CityでPlurality本の内容を可視化×bertopic×bertopic:_neural_topic_modeling_with_a_class-based_tf-idf×UMAP×hdbscan×mashbean×初探_polis_2.0:邁向關鍵評論網絡×熟議×レジリエンス×双方向的マスコミュニケーション×国民ラジオ×一方向的マスコミュニケーション×聞く姿勢×デジタルネイティブは4年に1度のアップロード帯域で十分とは思わない×雪玉×polis_2.0×発想法×川喜田二郎×kj法×凝集型階層的クラスタリング×u理論→

- →Talk to the City×brittney_gallagher×deger_turan×ai_objectives_institute×silent_cry×社会復帰の課題×技術へのギャップ×雇用障壁×メンタルヘルスサポート×whatsapp×mashbean×障がい者×社会的弱者→
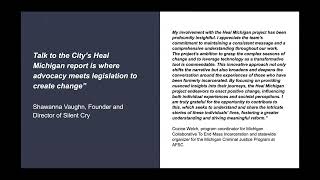
- →Talk to the City×polis×mashbean×plurality×100分de名著_ローティ『偶然性・アイロニー・連帯』×日記2024-02-07×日記2024-02-09×日記2023-10-31×日記2023-02-08→
- →渾沌をして語らしめる×学びて時にこれを習う×學而時習之、不亦説乎×探検の五原則×問題提起ラウンド×状況把握ラウンド×本質追求ラウンド×語るkj法図解×クラスタとの会話×Talk to the City×植え替えノート×移植×時の試練×kozaneba読書→
"Engineer's way of creating knowledge" the English version of my book is now available on [Engineer's way of creating knowledge]

(C)NISHIO Hirokazu / Converted from [Scrapbox] at [Edit]