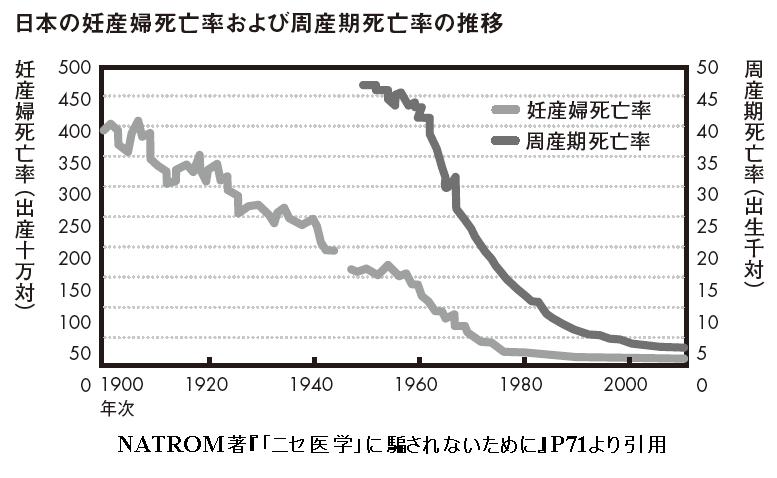意外性がないと書くことがなくなる
>最近Devinの話をあまり書いていないのは、使わなくなったからではなく、普通に日常的に使っているから特に書こうと思う出来事がなくなってきたせい from Devin.aiを試す4/1~
「質が向上すると見えなくなる」の要因を「AIの仕事いっぱいし始めるとAIについて喋れなくなる」だと思っていたが、それだけではなく、「XをしたらYになるだろう」と思って、やって、実際Yになったときに、本人としては当たり前だから書くモチベーションがないんだよな
技術自体の進歩によって抽象化のもれる穴が小さくなることで、結果のばらつきが減っていく
使い手がその技術に習熟していくことで、どういうことができるかの見積もりが正確になっていく
期待値コントロールが自分に対して働く
たとえば自転車に初めて乗れた時は「自転車に乗れた!」と話すし、しばらくは「自転車に乗れるようになったことでいままで行けなかったこんなところに行けるようになった!」とか話すけど、そのうち自転車に乗れることも、自転車に乗ればそこに行けることも当たり前になり、話す気が起きなくなっていく
4oのイラストも最初は想定以上だった
毎日ChatGPTを使ってるし、ほぼ毎日Devinも使ってるけど、それはわざわざ書くことはない
AIが予想外にバカなことをした時も意外性があるので書く機会になる
振る舞い予測力が上がるにつれて意外性が減る
この「使い始めのシグナリングの時期」がすぎると、知る機会が減っていく
"Engineer's way of creating knowledge" the English version of my book is now available on [Engineer's way of creating knowledge]

(C)NISHIO Hirokazu / Converted from [Scrapbox] at [Edit]