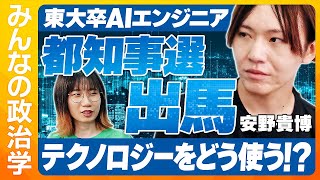Kozaneba:Plurality
>@nishio: 意味わからんなーと思ってた「プルーラリティ」に関して、目下のところ僕の中でのハンドルとしての言葉は「デジタル技術による複数性」になっている
>nishio わからないことメモ: グレンの所属
>@0xtkgshn: @nishio マイクロソフトリサーチ
>@0xtkgshn: @nishio 今思ったんですけど、サイボウズラボの西尾さんみたいな感じかもです笑笑
>@0xtkgshn: @nishio 話変わりますが、これにインスピレーションを受けたのがDeCartographyです
>nishio システム的にはほぼ同じか
>0xtkgshn Pol.isを使ったvTaiwanという関係性です。例えばRadical X Change のRxC Voiceとかと、同様にPol.isを埋め込んでいます。
>nishio Polisがオープンソースだから色々なところで部品として使われているというわけね
>nishio 3/29に描いたこれを国のレベルでやったのがvTaiwanということだな
>nishio "reshape how we govern the public and private sectors"と書いてある。
> 僕はグループウェアの会社の研究部門の人間として、つい企業や、自治体であっても「自治体職員」という塊を組織の境界として捉えてしまっていたが、地方自治体とその地方の住民を一つのチームであるとみなすと同じ形になる
>nishio 「移動式投票」と言った時に、投票対象の粒度を国と捉えていると、大部分の日本人にとって国外への移動が言語的ハードルとセットになって辛い的な話になるけど、日本国内の自治体の粒度で考えれば難しくないし既に行われてる。明石市の流入超過9000人
>nishio 続き
>@nishio: Pluralityの段階では「業務上有益な概念」という感覚だったものが「ブロードリスニング」になって急にテンションぶち上がりになるの、やっぱ僕は本質的に「人間の知的能力の強化」に関心があるのだなぁという気持ち
>人間の「大勢の意見を認識する能力」を増強したら「よりよい合意形成」ができる
>@nishio: 人間が「大勢の意見を認識する能力」が低いがゆえに意見の差に「敵」を見出したり、互いに相手を少数派だとか馬鹿だとか思ったりする。そこを強化してやればより良い合意形成ができる。なるほど確かにこれはcollective intelligenceだ。
>@nishio: 人類に比べて圧倒的に賢いAI「単一」「シンギュラリティ」による独裁制統治に対する対立概念として、「多様」な立場の「複数の」人間の「デジタル」技術による強化とより良い「社会的選択」「合意形成」のメカニズムデザインによる共和制統治を目指すムーブメントということかな〜??
>@nishio: 平和な日本にいると、政府に握られていないアイデンティティによって集会の自由や結社の自由が得られるというところ、それが重視されるような大変な状況なのだなというのは頭ではわかるが、切迫感はなかなか共感しづらいなぁ
>AIが中央集権的な監視と結びついて解釈されてるのとかも理由はわかるが…
Related Pages
- →星_賢人×矢島_美代×矢野_和男×algebraic_quantum_intelligence:_a_new_framework_for_reproducible_machine_creativity×ブロードリスニング×2025年のブロードリスニング×aiが仲介するコミュニケーション×PluralityとPolis勉強会×LLMがもたらす組織構造の変化×2024-09-08-民主主義を支える技術×100人いれば100通りの幸せ×100人100通り×audrey_tangと垂直・水平×d/acc×台湾で選挙期間に中国によって与党不利な印象操作がされた×新たな冷戦×山岡_仁美×権_永詞×齋藤_紘良×簗田寺×橋と扉×ゲオルク・ジンメル×レンマ学×swgs×クライミング×チッピング×鬼頭秀一×社会的リンク論×アンドレアス・レクヴィッツ×独自性社会×個人化社会における文化的分断×新しい中産階級×古い中産階級×主観的ウェルビーイング×暇×足るを知る×動きを作る×協同組合×モンドラゴン協同組合×現金はコモディティ×龍樹の四句分別×湧き出し×倍速会議×singularityではなくpluralityという未来v2×plurality本ジュンク堂池袋本店政治部門年間ランキング1位×when_we_hear_“the_singularity_is_near”,_let_us_remember:_the_plurality_is_here×plurality_means_technology_to_foster_the_diversity_in_society_and_the_collaboration_across_those_diversities.×gpqa_diamond×計画経済×全体最適主義×意思決定×共有地の悲劇×エリノア・オストロム×connections_between_indivisuals_as_first-class_objects×intersecting_group×ハンナ・アーレント×人間の条件×ダニエル・アレン×connected_society×オードリー・タン×ゆるコンピュータ科学ラジオpolis回×⿻_plurality_&_6pack.care×ケアの倫理×興味関心によって集まったデジタルの「地域」×pluralityは無色の新語として作られた×自己紹介×少し後ろをついて行くのは容易→
- →日記2025-02-17×singularityではなくpluralityという未来×plurality×シンギュラリティ×kiite_world×ランキング×アテンション×視聴体験の多様性×多様性×連想のネットワーク×集めて接続×新しい公衆×行政と民間が協働で“新しい公”を創る。govtech東京が描く、新たな社会とは|govtech東京公式note×空気抵抗×技術的特異点×終端速度×d/acc×2025-02-16サンデージャポン→
- →audrey_tang(2016)×plurality_poem×智慧聯網×實境共享×協力學習×體驗人際×奇點×數位×mandarin×glen_in_japan_keynote日本語字幕×モノのインターネット×internet_of_things×智慧のインターネット×萬物聯網×仮想現実×virtual_reality×共有現実×現実共有×虛擬實境×機械学習×machine_learning×協調学習×collaborative_learning×ユーザーエクスペリエンス×体験共有×間主観性を体験すること×間主観性×シンギュラリティ×plurality×協働的多様性×多元宇宙×協力学習×ポエム→
- →pol.isでのuberの議論×vTaiwan×uber×オードリー・タン×uber_responds_to_vtaiwan’s_coherent_blended_volition×polisは返信をなくした×リプライできない仕組み×イデオロギーは「心のウイルス」→
- →安野_貴博×鈴木_健×東_浩紀×プルラリティ×ゲンロン250626×ised×デジタル民主主義2030×アメリカ大統領選2024ロードトリップ×ハンナ・アーレント×革命について×革命×自由の創設×タウン・ミーティング×評議会×natality×政府効率化省×doge×なめらかな社会とその敵×21世紀のイデオロギー×差異があるという意味において平等×協力の深さと広さのトレードオフ×pluralityとハイプカーブ×ハイプカーブ×community_notes×pol.is×pol.isでのuberの議論×Quadratic Voting×quadratic_funding×talk_to_the_city×ブロードリスニングが国会で野党が総理大臣に質問するために使われた事例×ハーバーガー税×joi_ito×創発民主制×weblog×草の根の民主主義×emergent_democracy×伊藤穣一×ブログ×rss×双方向メディア×下からの自己組織化×歴史は循環する、しかし内容はより高次のものとなる×似た物が昔にもあった型思考×テクノ封建制×civilization×東京大学pluralityセミナー2025-05-12×統合テクノクラシー×企業リバタリアニズム×デジタル民主主義×ブロードリスニングが1年で標準戦略に×ひまわり学生運動×radicalxchange×why_i_am_not_a_market_radical×plurality(2022)×pluralityは無色の新語として作られた×tokyo_plurality_week_2025×d/acc×マルクス主義×加速主義×柄谷行人×世界史の構造×マルクスその可能性の中心×探究_ⅰ×誤配×ルクレティウス×ずれ×すべてのものには裂け目がある。そこから光が差し込む×違いを越えて協働するための技術×一般意志×全体主義×単一性×エロイーズ×訂正可能性×垂直的×単一的×カール・シュミット×カール・シュミットの「議会批判」と「独裁」論×コネクテッド・ソサイエティ×ダニエル・アレン×規範的plurality×アジェンダ設定の権限を人々に開放する×請願権×オンライン請願×james_s._fishkin×詐欺犯罪危害防制條例×mini-public×いどばた政策×stanford_online_deliberation_platform×forkability×正統性×自己主権型アイデンティティ×伊藤_孝行×安野チーム台湾報告会×audrey+glen+colin+pmt研究会×【オードリータン✖️小川淳也】未来を共創するデジタル民主主義×玉木雄一郎+plurality×愚行権×audrey+tbs_cross_dig×裏ハイデガーとしてのアーレント×今北勢問題×訂正可能性の哲学×家族性×家族×動的な認知的膜×ホロン×クリプキのクワス算×truth_social×政治家は猫になる×社会資本が王である世界×アテンションエコノミー×贈与経済×台湾の同性婚は親族にならない×2ステップの熟議×アーレントのwork×ファンダム→
- →まず泥臭い問題解決で信頼醸成×外部からいきなりctoとして就任する時に気をつけていること×後から来た人間は先にいた人間の信頼を獲得する必要がある×u曲線モデル×既存のシステム×すり合わせ×既存システムをリスペクトする×リスペクト×評価関数の違い×個人の尺度×協調コスト×法的リスク×組織の尺度×キャリア・トラックの非対称性×起業志向×スピード×独自性×安定志向×再現性×合意形成×摩擦コスト>成果×若年期ボーナス×失敗回数の多さ×尖った言動×失敗許容量×信頼資産×リスクテイク×連帯コスト×巻き添えロス×火消し対応×信頼回復×総コストに対する総価値×コミュニケーションの問題は互いに問題がある×信頼のネットワーク×板挟み×信頼の低下×紹介者責任制×連帯保証人×コミュニティに有害な人はコミュニティに誘われない×みずから引き起こした疎外×殺す人間の世界は広がらない×社会資本の拡大再生産×社会関係資本の使い方×u理論×downloading×思い込みの枠×presensing×ソーシャルフィールド×performing→
- →なめ敵会×なめら会議×鈴木健×ikkun×なめらかな社会とその実装×ぬかどこみたいなコミュニティ×ryoar×妄想による発展×sfプロトタイピング×sowawa×sur40×マークアップ率×障壁を取り除く=なめらか化×似ている→違いは?×pinterest×雑だが有益×雑×retroactive_funding×成果が出た後で評価する方が容易×何が役に立つかよりも、何が役に立ったかについて合意する方が簡単×死んだテキスト×死んだ知財×知識はネットワークで保存される必要がある×memex×常緑のノートはアトミックであるべき×有用な概念の当たり判定を拡大する×物権法的主義×story_protocol×ルソー×人間不平等起源論×ノウアスフィアの開墾×radical_markets×molecule×lightning_labs×toshiya_tanaka×時間軸のマージ×自分などというものはない×核と膜の構造から脱する×制御という幻想×quic×tcp×udp×今はプログラミングが生まれて最初の1世紀×加速思想×断続平衡説×なめ敵×柄谷_行人×贈与の共同体×エコヴィレッジ×dedeal×メルカリ×decentralized×centralized×誰も強制されない×ネットワーク効果×内在的闘争と超出的闘争×超出的×暇と退屈の倫理学×ポスト稀少性時代×moore's_law_for_everything×solidity_house×濱田_太陽×desci_tokyo×chugai_innovation_day_2023×funding_the_commons×tkgshn×protocol_labs×innovation_commons:_the_origin_of_economic_growth×radicalxchange×glen_weyl×audrey_tang×vitalik_buterin×plurality×全体主義の起源×全体主義×ボーグ×radicalxchangeの”x”×交換様式×交換様式論×トランスクリティーク×認知の解像度×闘技民主主義×敵味方なくなると全体主義になる×闘技×民主主義には競争性が必要×集まるのが最初の一歩、一緒に居続けるのが進歩、一緒に働くのが成功×習合×貨幣論×岩井_克人×マルクスその可能性の中心×探究(柄谷_行人)×貨幣の自成と自壊×安冨_歩×恐慌論×ハーバーマス×社会システム理論×オートポイエーシス×ノウアスフィアの開墾と交換様式論×nam×lets×ハンナ・アーレント×カール・シュミット×pluralityとなめ敵には家族的類似性を感じる×家族的類似性×バタイユ×コミュニオン×貨幣は0記号×humor_over_rumor×Polis×community_notes×水銀を飲んで不老不死×メカニズムデザイン×物神×モースの贈与論×ハウの精霊×ハウの呪力×情報は情報発信者に集まる×6次の隔たり×シグモイド関数×アローの定理×未踏×物価とは何か×ブログが解体されsnsとscrapboxになった×sui×aptos×libra×共創の前にまず独創×ブロードリスニング×孫正義×21世紀のイデオロギー×スピンアウト×良いものを移動させる×エンロン×sox×j-sox×未踏と日本版バイドール法×竹内_郁雄×前川_徹×産業活力再生特別措置法×日本版バイドール法×与謝野_馨×萩原_崇弘×未踏ソフトウェア創造事業×為末_大×人生100年時代の社会保障とpolitech×非目的論的ないじくり回し×境界のなめらか化×あいまい化×ファジー集合×会社境界の曖昧化×キャンプファイヤー経営×東_浩紀×観光客の哲学×nostr×自分の成果物を自分で使え×オーナーシップ×辺境×反出生主義×スイスは自殺幇助が合法×最大多数の最大幸福×幸福の合理的追求×自由からの逃走×自由意志×自我×テセウスの船×還元主義×リベットの実験×世界公務員×量子力学的ロシアンルーレット×運が良い×人間原理×メタ認知×唯識思想×十牛図入門×worldcoin×ubi×worldcoinはガバナンストークン×decentralized_id×paypayは100億円あげちゃうキャンペーンで規模を拡大した×aiとの共生×同型性の宇宙:生命から政策まで×複雑系への適応として見る「なめ敵」とplurality→
- →Pluralityとは×協働できる多様性×民主主義×plurality×radicalxchange×radical_x_change×⿻_數位_plurality:_the_future_of_collaborative_technology_and_democracy×plurality:_the_future_of_collaborative_technology_and_democracy→
- →サイボウズラボ勉強会×尾鷲2024-01-23~24×plural_management×Quadratic VotingとPlural Management勉強会×quadratic_mechanism×階層的な組織の権威×ネットワーク化された権威×pluralなメカニズム×実力ベースの権力構造×オープンソースソフトウェア開発×価値ある貢献×勤勉さ×参加×適応的な集合知×plurality×二次的メカニズム×オープンソース×ソフトウェアマネジメント×組織力学×glen_weyl×gov4git×Quadratic Voting×Quadratic Voting: How Mechanism Design Can Radicalize Democracy×quadratic_funding×tyranny_of_structurelessness×ostrom_and_hess,_2011×社会的手抜き×公共財メカニズム×意思決定におけるボトルネック×才能の未活用×top-down_approach×上意下達×ボトルネック×ティール組織×メカニズムデザイン×二次関数的なコスト関数×予測市場×オークション×plural_management_protocol×collusion×beyond_collusion_resistance:_leveraging_social_information_for_plural_funding_and_voting×慈悲深い独裁者×フォークできるなら政治は不要×すべてのフォークは存在を許され、どのフォークに関心を持つかは周囲のコミュニティに委ねられる×誰も強制されない×社会制度をフォークする×g0v×民主主義はリアルタイムシステムへと進化する必要がある×social_inovation_legitimates_governance×ボタンが大量についたテレビのリモコン×メリトクラシー×アンダーマイニング×ちぎれる→
- →funding_the_commons×funding_the_commons_tokyo×ftctokyo×公共財×資金分配×ftctokyo_day1×ftctokyo_day2×濱田_太陽×分散型科学×desci×デジタル公共財×分散型技術×オープンソースソフトウェア×オープンサイエンス×研究自動化×メカニズムデザイン×研究の未来を探索する×世界規模のヴァーチャルラボ×分散型データ共有×特許流通基盤×探索的研究の支援システム×守_慎哉×クリプト×公共財への資金提供×public_goods_funding×集団の意思決定×寄付のプラットフォーム×dao×decentralized_autonomous_organization×オンチェーンガバナンス×プログラムによる自動執行×人間同士の調整問題×偽アカウント問題×結託×持続的資金不足×無関心×インパクト評価不足×code_for_japan×関_治之×オープンデータ×オープンaiモデル×資金調達モデル×政府助成金×民間寄付×シビックテック×sdgs×グローバルな課題解決×高木_俊輔×tkgshn×統治技術×社会実装×protocol_labs×edcon×再生ビジョン×ai_alignment×ossの資金調達×depopulation×d/acc×civichat×govtech→
- →アダム・カヘン×小田理一郎×plurality×社会的差異を超えた協力×ファシリテーター×変容的シナリオ・プランニング×パワーと愛の両輪×敵と協働する×ともに前進できる最小限の方向性×ファシリテーション×垂直型ファシリテーション×トップダウン×指揮命令×水平型ファシリテーション×ボトムアップ×合意形成×変容型ファシリテーション×力と愛×貢献とつながり×チームの知的生産性の向上×コンテクスト×メンバーの関係性×場の質×結論を出す×前に進む×ネガティブケイパビリティ×主体性×当事者性×障害を取り除く×神秘の出現に対する障害を取り除く×貢献・つながり・平等×敵とのコラボレーション×社会変革のシナリオプランニング×open_space_technology×u理論×未来を変えるためにほんとうに必要なこと×自己実現に駆り立てる力×再結合へと駆り立てる愛×垂直型ファシリテーションと水平型ファシリテーションはどちらもコラボレーションを制約する×民主的×水平型×垂直型×呼吸のたとえ×アウターゲームとインナーゲーム→
- →Funding the Commons Tokyo 2024×Plurality in Japan×ftctokyo!×ftctokyo×talk_to_the_city×audrey_tang×glen_weyl×Plurality: Technology for Collaborative Diversity and Democracy×チームワークあふれる社会を創る×理想への共感×100人100通りの働き方×100人100通りの人事制度×デジタルツール×多様性×funding_the_commons×柄谷行人×交換様式論×デジタル民主主義×交換様式a×colors.js事件×beyond_public_and_private×安宅_和人×intersecting_group×21世紀のイデオロギー×統合テクノクラシー×企業リバタリアニズム×ブロードリスニング×主観か客観かではなく、一人の主観から大勢の主観へ×vTaiwan×Polis×メディアとしてのグループウェア×生産性向上ソフトウェア×ソーシャルメディア×一丸となって共通の目標を達成×変化に適応×プロソーシャルメディア×グループウェア×副業×複業×パラレルワーク×理解され、実行されるまでの時間を短縮する×アジェンダ設定の権限×参加型政策立案×参加型予算編成×majority_judgement×Quadratic Voting×kj法の累積的効果×vTaiwanでUberに関する議論がどう進展したか×Meetup with Audrey & Glen×audrey+glen+halsk@cybozu×未来はすでにまだらに存在している×組織の境界×なめらか化×開門造車、你行你来×思惟経済説×plurality質疑@ftctokyo→
- →メカニズムデザイン×資源配分×インセンティブ×坂井_豊貴×藤中_裕二×若山_琢磨×マスキンの定理×耐戦略性の定義×ゲーム理論×支配戦略均衡×直接ゲーム×直接メカニズム×社会的選択関数×解概念×メカニズムの定義×メカニズム×非拒否権性×ベイジアン誘因両立性×社会的選択×ソロモン王のジレンマ×グレーザー=マーメカニズム×社会的選択対応×ナッシュ遂行×耐戦略性×支配戦略遂行×無支配戦略遂行×公共的意思決定×ギバート=サタスウェイト定理×無作為独裁制×グローヴス関数×期待外部性関数×交換経済×ワルラス配分×ハーヴィッツ定理×制約ワルラス配分×第二価格オークション×セカンドプライスオークション×収入同値定理×最適オークション×公平分担×非分割財交換×トップトレーディングサイクルアルゴリズム×コア(ゲーム理論)×マッチング×ゲール=シャプレーアルゴリズム→
- →vitalik_buterin×メカニズム×アルゴリズム×インセンティブ×credible_neutrality_as_a_guiding_principle×メカニズムデザイン×メッセージ空間×配分関数×移転×インセンティブ整合性×メカニズムの定義×メカニズムデザイン(書籍)→
- →plurality_tokyo_namerakaigi×サイボウズラボ勉強会×pol.is×community_notes×メカニズムデザイン勉強会×majority_judgement勉強会×PluralityとPolis勉強会×polis勉強会×Quadratic VotingとPlural Management勉強会×Talk to the City勉強会×世論地図勉強会×高次元データ分析勉強会×デジタル民主主義研究ユニット×ピボット×古典期アテネの民主主義のスケール×国民こそが唯一の正統な権威である×フランス革命×フランスでの女性参政権×一人一票×未成年者には投票権がない×成年被後見人の選挙権×ドメイン投票方式×デメニー投票×デーメニ投票×Quadratic Voting×glen_weyl×qv×radical_markets×audrey_tang×vitalik_buterin×quadratic_funding×audrey_tangのqv×glen_weylのqv×quadratic_votingがシナジーの発見に有用×台湾総統杯ハッカソン×qvは投票しないことに意味のあるメカニズム×「投票しないことは良くないことだ」は根拠のない思い込み×vitalik_buterinらのquadratic_funding×a_flexible_design_for_funding_public_goods×akb48総選挙×gitcoin×gitcoin_grants×公共財×リソースの再分配×社会的意思決定×メカニズムデザイン×多数決×くじ引き×抽選制×抽籤制×プラトン×アリストテレス×ジェームズ・マディソン×ジョン・スチュアート・ミル×アレクシ・ド・トクヴィル×選挙は4年に一度5bit送信する遅い通信だ×ブロードリスニング×Polis×pol.isでのuberの議論×metaがファクトチェックを廃止×community_notesにおける行列分解を用いた信頼度スコアリング×多様な主体から支持されることを評価する仕組み×talk_to_the_city×日テレnews×2024衆院選×ブロードリスニング×シン東京2050ブロードリスニング×umap×世論地図×mielka×2024衆院選×japan_choice×meta-polisの構想×mashbean×協力の深さと広さのトレードオフ×plurality本×aiあんの×タウンミーティング×非同期化×空間と時間の制限から解き放つ×chatgptとaiあんののコミュニケーションの形の違い×ai政治家の3つのレベル×aiが間に入って非同期化×open_space_technology×アジェンダ設定の権限を人々に開放する×vitalik×主観主義×3つのイデオロギーの間に2つの対立軸がある×aiが仲介するコミュニケーション×bluemo×intersubjective_model_of_ai-mediated_communication:_augmenting_human-human_text_chat_through_llm-based_adaptive_agent_pair×時間の制約×心理的安全性×緩やかに繋ぐ×デジタル民主主義2030×同じ時間と場所を共有できない人に機会を用意×metapolis×スケーラビリティ×デジタル民主主義×コミュニティ×大規模コラボレーション×xy問題×熟議のための4つのステップ×リプライはスケールしない×リプライさせない×your_priorities×コトノハ→
- →十分の一税×tithing×税金×投票×市場×quadratic_funding×conviction_voting×retroactive_public_goods_funding×nft×ネットワーク財×network_goods×効果的利他主義×effective_altruism×ハイパーサート×hypercerts×augmented_bonding_curve×dominance_assurance_contracts×donation_mining×budget_box×ペアワイズ評価×futarchy×stigmergy×demurrage×Quadratic Voting×joke_race×web3空間×メカニズムデザイン×くじ引き×sortition×staking×slashing×proof_of_work×sybil_resistance×web3_social×the_regen_space→

- →plurality×サイボウズ×audrey_tang×glen_weyl×Plurality: Technology for Collaborative Diversity and Democracy×コラボレーション×多様性×多様な人々が協力して物事を成し遂げていくための技術×チームワークあふれる社会を創る×チームワーク×100人100通り×共感×理想への共感×ブロードリスニング×主観か客観かではなく、一人の主観から大勢の主観へ×vTaiwan×Polis×メディアとしてのグループウェア×生産性向上ソフトウェア×ソーシャルメディア×一丸となって共通の目標を達成×変化に適応×プロソーシャルメディア×グループウェア×デジタル民主主義×理解され、実行されるまでの時間を短縮する×アジェンダ設定の権限→
- →pol.is×コトノハ×loomio×stanford's_opinion_space×supporting_reflective_public_thought_with_considerit×your_priorities→
- →投票×メカニズムデザイン×1p1v×1_person_1_vote×一人一票×Quadratic Voting: How Mechanism Design Can Radicalize Democracy×デジタル民主主義×民主主義→
- →audrey_tang×halsk×真鶴×アレグザンダー×パターンランゲージ×美の条例×建築基準法×観光地化×公共財×共有地の悲劇×手を加えることに対する気後れ×どのようにアップデートしていくか×高齢化×高齢化率×要介護率×和光モデル×贈与経済×望春風×social_inovation_legitimates_governance×nishikigoi_nft×ブロードリスニング×人間増強×コンセンサス×空気が支配する日本ではブロードリスニングが重要×ソーシャルイノベーションが統治を正統化する×ethereum×スイッチングコスト×ウクライナ×シビックテック×taiwan_ready_to_assist_ukraine_with_digital_reconstruction×politicsとtechの連携×ゼロサムゲーム×anthropic×コンテキスト長×言語マイノリティ×物ができてから評価する方が楽×移動式投票×事後的に統治方法が正統化される×遅いシステムの移行先としてのdapps×ロックイン×portable×interoperable×ai学習パートナー×decidim×Polis×市民参加プラットフォーム×個人認証×中銀カプセルタワービル×式年遷宮×国際社会はアナーキー×デジタル公共財×collective_action×インセンティブ設計×ナッシュ均衡×人気のものに課税し公共財に投資する×patagonia×ソーラーシェアリング×「課題感」と「解ける課題」は別物×live_long_and_prosper🖖×真鶴出版×オードリー・タン→
- →⿻數位_plurality×plurality_tokyo×plurality×數位×多元×多元主義×多元宇宙課×プルーラリティ×多元性×複数性×audrey_tang×e._glen_weyl×共働的×多様性×民主主義×vTaiwan×Quadratic Voting×quadratic_funding×gitcoin×ある概念が既存の言葉で簡潔に説明できるなら、それは新しい概念ではない×分散id→
- →plurality_tokyo×気流舎×言葉のplurality×why_i_am_a_pluralist×long_is_good×輪廻転生×死生観×snsの分裂×activitypub×bluesky×threads×相互運用性×移動式投票×主観主義×ラストワンマイル×宗教的多元主義×認識論的多元主義×シルバー民主主義×対立を煽るな×対立を煽る×煽る×対立から目を逸らす×アウフヘーベン×一人一票×拡大しない価値観×変わるインセンティブ×パレート最適への道×移動式投票による東京一極集中×フォーク×沈みゆく船に残るか、氷山にぶつかるか×分人×picsy×duolingo×自分たちの文化を発信したい×共通の価値観×徴税能力×taxation×wideプロジェクト×所得分配契約×nostr×irc×移動と革命×領土を必要としない国家×未成年者に投票権を与えないことは不平等×civichat×公共財×持続可能な方法で資金を分配×plurality_tokyo_salon→

- →サイボウズラボ勉強会×メカニズムデザイン×メカニズムデザイン(書籍)×メカニズムデザインで勝つ×耐戦略性の定義×公明正大×効率性の定義×ベイジアン誘因両立性×非羨望性×top_trading_cycleアルゴリズム×強コア配分×ゲール=シャプレーアルゴリズム×ソロモン王のジレンマ×グレーザー=マーメカニズム×三原=チン=ヤンメカニズム×情報の非対称性×第二価格オークション×弱支配戦略×ゲーム理論〔第3版〕×スマートコントラクト×一般化受入保留アルゴリズム×majority_judgement×ギバート=サタスウェイト定理×マスキン単調性×独裁的×単峰的選好×メカニズムの定義×トップトレーディングサイクルアルゴリズム×非集中的→
- →多様性×世界×システム×単一×異なる要素×異なる視点×共存×多様×相互作用×柔軟性×発展×進化×チャールズ・ダーウィン×進化論×自然淘汰×アイザイア・バーリン×価値の多元論×複数の価値観の共存×ジル・ドゥルーズ×差異と反復×存在の根底にある多様性×ウィリアム・ジェームズ×経験の多様性×認識の多様性→
- →新しい知識×多様×共通の考え×世界は元から多様である×交換様式論×伽藍とバザール×排他的クラブ×同温層×レクリエーション×心のエネルギー×バザールは不愉快な人と出会うことを妨げられない×不快なバザール→
- →サイボウズラボ勉強会×plurality_in_japan(サイボウズラボ)×Funding the Commons Tokyo 2024×Talk to the City勉強会×tttc:_aiと著作権に関するパブリックコメント×サイボウズと語ろうplurality_多元性の実践と期待×2024-09-08-民主主義を支える技術×ブロードリスニング×meetup_with_thomas_hardjono×ソーシャル物理学×テクノロジーとわたしたちの「距離感」が変われば、誰も取り残されない社会がつくれるかもしれない×デジタル民主主義×ブロードリスニングの「あの図」×階層組織×ティール組織×個人情報とマネタイズ×成蹊大学×2019年度武蔵野市寄付講座「itとルールの今・未来」×計画経済×LLMがもたらす組織構造の変化×ブラウン組織×plurality_tokyo×PluralityとPolis勉強会×主観か客観かではなく、一人の主観から大勢の主観へ×情報の複製により情報発信は効率化されたが、受信は改善しない、情報を減らす技術が必要×関_治之×激動の2024年5月下旬×ミーム化×asia_blockchain_summit_2024×サイロ化×組織の境界×なめらか化×Plurality in Japan×良い議論ができる場を可視化の後につける×可視化×aiあんの×u理論×ソーシャルフィールドを耕す×mashbean×dx&ai_forum_2024×生成aiで作るデジタル民主主義の未来×「聴く」「磨く」「伝える」のサイクル×human_in_the_loop×people_in_the_loop×オモイカネ勉強会×chatgptとaiあんののコミュニケーションの形の違い×社会的学習×アイデアの流れを混ぜてアイデアの多様性を増す×組織としての学習×集団的知性×複数組織とブロードリスニング×個人的文脈×当事者意識×ファウンダーマーケットフィット×熱意×proj-broadlistening×social_hack_day→
- →対立は恐れずに活用すべきエネルギー×airbox×相互運用性とスーパーモジュラリティ×quadratic_votingがシナジーの発見に有用×参加者が多いほど良いシグナルが得られる×地元発のプロジェクトを全国インフラ化する×多様な意見の橋渡しの価値が高い×joinでの賛成反対2カラム表示×署名した人にメールを送り、オンライン会合に来る人を募る×台湾の詐欺防止法におけるデジタル署名×help_the_helpers×10代の若者によるオンライン請願×trustlessではなくtrust-building×抗議とデモの違い×公共財×スーパーモジュラリティ×組み合わせによる相乗効果×vTaiwan×join.gov.tw×デモ×解決策の提示×二次投票×Quadratic Voting×デジタル署名×did/vc×pol.is×talk_to_the_city×橋渡しボーナス×橋渡し×トラストレス×ブロードバンドは人権→

- →情報処理×新時代の道具,_chatgpt:14_の視点からその可能性を探る×chatgpt×一人の主観から大勢の主観へ×主観か客観か×誤った二項対立×chatgpt_api×陳腐化×抽象度の高い知識×具体的経験×みずからの目で見なければならない×根無し草の知識×今開いている扉が未来も開いている保証はない×幸運の女神には前髪しかない×エンジニアの知的生産術×知的生産性の向上×人間増強の四要素×概念のハンドル×取っ手×(column)_パターンに名前を付けること×(4.5.3.3)_思考の道具を手に入れる×発想法×方法論×名前×一部が消えて一部残り新しく生まれる×思考の結節点2023-02-23×chatgptに「質問を繰り返す聞き手」の役割を演じさせる実験×クリーンランゲージ×かんがえをひきだすチャットボットkeichobot×scrapboxに住んでるエージェント×aiの住んでるscrapbox×ai質問箱uiについて考える×自分のscrapboxをchatgptにつないだ×scrapbox_chatgpt_connector×自分のscrapboxをchatgptにつないだ話勉強会×aiパネルディスカッション×scrapboxはアイデアの精製器×エミュレータ×書籍とは双方向のコミュニケーションができない×仮想人格とのブレインストーミング×正しさと有用性は別物×異なる視点×盲点×気づく×すべてのデータはうそである×円柱は円にも四角にも見えるが、円でも四角でもない×コントロールできることに力を注ぎ、コントロールできないことは気にしない×コストが下がれば構造が変化する×plurality×audrey_tang×シンギュラリティ×ブロードリスニング×熟議×熟議のための4つのステップ×Polis×sentiment_gathering_platform×認知能力の限界×人間増強×情報の複製により情報発信は効率化されたが、受信は改善しない、情報を減らす技術が必要×PluralityとPolis勉強会×シビックテックによる、社会と民主主義のアップデート×階層構造×中間管理職×間接民主制×代議士×デジタルネイティブ×選挙は4年に一度5bit送信する遅い通信だ×デジタルネイティブは4年に1度のアップロード帯域で十分とは思わない×まだ言語化されていない知識×文明に対する貢献×既に言語化された知識×世界とaiのインターフェース×世界をセンシングしてaiに与える仕事×まだ書かれていないことの森を切り拓いていく仕事×aiが読めない形での情報発信は価値が下がっていく×フォーク×正統性×投票×移動式投票×主観主義×Panarchy×arxiv×査読×品質担保×情報共有の速度×オープンアクセス×有用性×大勢の主観×品質より速度×文明の乗り物×人間は一時的キャッシュ×accessism×openai×democratic_inputs_to_ai×anthropic×スケールする熟議×scalable_deliberation×opportunities_and_risks_of_llms_for_scalable_deliberation_with_polis×community_notes×主観的×オモイカネプロジェクト×主観か客観かではなく、一人の主観から大勢の主観へ:Q&A×chatgptについてのコラムの準備×chatgptについてのコラムの準備2→
- →熟議の概念について解像度を高める×ジャン=ジャック・ルソー×ルソー×一般意志×社会契約論×合意形成×the_social_contract×volonté_générale×一般意志は、市民全員が公共の利益を熟慮した結果として形成される×直接民主主義→
- →スマートニュース×なめらかな社会とその敵×なめ敵×なめ敵会×picsy×なめら会議×異世界転生としての別コミュニティ突入×小口化×radical_markets×partial_common_ownership×salsa×gradualとpco×ステップな市場×組織の境界×top_trading_cycleアルゴリズム×dedeal×toori_mo×ルソー×人間不平等起源論×暴力が正義を作る×エコン×観察者の存在が互恵性の維持に重用×コミュニティによる生産性向上のすすめ×正義のゲーム理論的基礎×分散型エスクロー×ekyc×non-custodial×sowawa×reality.eth×foteison×達成できたら解散×老害×式年遷宮×逃げ続けるsns×unipos×nam生成×propagational_proxy_voting×decidim×Polis×合意形成×citydao×誤った二項対立×aml×自転車置場の議論×エントロピー増大の法則×均衡は不況×plural_qf×ネットワーク外部性×colors.js事件×ethereum×quadratic_funding×Quadratic Voting×gitcoin×plural_funding×soulbound_token×quadratic_votingはなぜ平方根を取るのか×一人一票×なめらかに共有するバーチャルな時空間×未来の自分に作業配信×メッセージ(sf)×オズマ問題×シルバー民主主義×主観主義×分割統治法×truthcoin×マージマイニング×マイクロスコープ×繋がっても距離は0ではない×ウェブサービスの提供拒否の権利×desci×松尾研×企業研究者×コールド・スプリング・ハーバー研究所×理化学研究所×財閥解体×ケンブリッジ市×市民参加型予算編組×ステーキング×全体主義×直接民主主義×splitdao×知識集権×柄谷_行人×世界史の構造×カリスマ的存在×vitalik×ナカモトサトシ×opportunities_and_risks_of_llms_for_scalable_deliberation_with_polis→
- →open_science_framework×再現性の危機×arnold_ventures×メタサイエンス×center_for_open_science×特許権×期限付き独占権×enforcement×デファクトスタンダード×pocとpmfは違う×データ共有基盤×公共的情報インフラ×インフラ×インフラの予算でやる×予備自衛官×コスモローカル×funding_the_commons×earth_commons×pagoda_thailand_builder_residency×パゴダ×co-creative×コロプラ×御代田×開発合宿×データ活用基盤×federated_learning×秘密計算×protocol_labs×ニューロテック×gitcoin×quadratic_funding×optimism×token_house×dao_treasury×インパクト評価×ebpm×トニー・ブレア×intervention×介入×評価システムも評価される×ビジョナリーにcooが必要×AOIのTTTCページにAudrey Tangのコメントがある×ワイガヤ×出しつくした感×焼きなまし法×認知的体力が無限大×熱意のある人はリソース×pagoda×4seas×フォーシーズ×コミュニティマネージャ×信頼の醸成×democratic_inputs_to_ai×プロセス評価×sib×事業仕分け×競争性×ウェルビーイングインデックス×ウェルビーイング×well-being×歯ブラシ問題×相互運用性×interoperability×幸福の定義×人々の幸福の定義は人間が行う必要性がある×サイボウズと語ろうplurality_多元性の実践と期待×aiによる統治×人間の意思決定×地域幸福度指標×デジタル庁×デジタル田園都市国家構想×移動式投票×曲線下面積×集団的意思決定×マッチング×レコメンド×複雑なものを複雑なまま理解する×2022年参院選のpolis的可視化×blu3mo×news_from_all_sides×つながり×昭和的価値観ai×polymarket×アイデアクラウド×hft→
- →legitimacy×正当性×justification×権威×authority×正当化×基礎付け×環境の変化が速くなると知識ではなく知性が信頼される×エスノメソドロジー×状況に埋め込まれた学習×正統的周辺参加→
- →未踏ジュニア夏合宿2024×記号の恣意性は人間が脳の外に持つ可塑性×ブロードリスニングは認知能力の増強×aiが統治する場合も人々の幸福の定義は人々が決めなければならない×連想のストック×external_links×人的ネットワーク形成システム×人材濃縮アルゴリズムが必要×組織境界の曖昧化×LLMがもたらす組織構造の変化×ホモサピエンスの枠を超えた知的生産主体の成長×都民の幸福に興味が待てない×文明進歩至上主義×日記2024-08-23×日記2024-08-25×日記2024-05-16×日記2023-08-24→
- →Funding the Commons Tokyo 2024×designing_for_plurality×presentation_script:_plurality_in_japan×知識ネットワーク×anno2024×LLMがもたらす組織構造の変化×経営者的思考×空気が支配する日本ではブロードリスニングが重要×erin_meyer×words_as_public_goods×beauty,_growth,_progress_--_all_result_from_the_union_of_the_unlike×川喜田二郎とブロードリスニング×かならず小分けから大分けに進まなければならない×発想法→

- →経営者というモンスターのエクスペリエンスをハックする×モンスター×LLMがもたらす組織構造の変化×PluralityとPolis勉強会×未踏的マインド×未踏×pm力×自分経営戦略×経営者視点×経営者目線×知識社会は上司と部下の社会ではない→
- →plurality_tokyo×audrey_tang×オードリー・タン×モノのインターネット×iot×存在のインターネット×仮想現実×vr×共有現実×機械学習×協調学習×ユーザーエクスペリエンス×ux×ヒューマンエクスペリエンス×シンギュラリティ×プルーラリティ×言語モデル×実存的リスク×アシスタント人工知能×独裁国家×協調的多様性×collaborative_diversity×deliberation×shared_values×みんなで熟考・熟議×コプレゼンス×フォーラム×公共広場×Quadratic Voting×規範的メカニズム×台湾総統杯ハッカソン×総統杯×河川管理プラットフォームlass×verifiable_credentials×decentralized_identifiers×world_wide_web_consortium×w3c×検証可能な資格証明×分散型id×台湾デジタル発展省が分散型idの標準化に参与×人間性の証明×quadratic_funding×retroactive_funding×ソーシャルインパクトボンド×長寿と繁栄を×熟議民主主義→

- →0か100か×物事を全か無かでしか捉えられない人×100%でないから価値がない×1bitの思考×試行錯誤は見えにくい×いいアイデアは複数の問題を一気に解決する×耳赤の一手×段階的な目標設定×良いアイデアは周囲の人を刺激し、自分で成長を始める×転がる雪玉×社会資本が王である世界×アーリーアダプター集団×今持っている知識の一歩先の知識しか受け止められない×他人が理解する前にポジションを取れ×自分の課題ではない×ひろゆき×舛添_要一×歴史の転換点×実験の民主主義×ファンダム化×宇野_重規×デジタル×ファンダム×結社×安野たかひろ×22世紀の民主主義×政治家はネコになる×デジタル民主主義×polis準備:_新しい民主主義×ドトール石丸×日記2024-06-25×日記2024-06-27×日記2024-03-18×日記2023-06-26→

- →サイボウズラボ勉強会×plurality_tokyo×plurality×ブロードリスニング×Polis×PluralityとPolis勉強会×polis勉強会×plurality_seoul×audrey_tang×gisele_chou×talk_to_the_city×ai_objectives_institute×deger_turan×aiと著作権に関するパブリックコメント×安野たかひろ氏が東京都知事選に出馬へ×マイナンバーカード×直接投票×オープンソース×デジタル公共財×人間増強×知的生産性の向上×都知事選でtalk_to_the_cityをする×tokyoai×主観か客観かではなく、一人の主観から大勢の主観へ×シビックテックによる、社会と民主主義のアップデート×手書きの図×polis:_scaling_deliberation_by_mapping_high_dimensional_opinion_spaces×polis体験レポート:同性婚を合法化すべきか×台湾の同性婚は親族にならない×vTaiwan×オープンガバメント×デジタル民主主義×透明性×参加型民主主義×アジェンダ設定の権限を人々に開放する×モデレーション×polisのモデレーション×AOIのTTTCページにAudrey Tangのコメントがある×集団的議論×集団的意思決定×peter_eckersley×electronic_frontier_foundation×let's_encrypt×certbot×privacy_badger×brittney_gallagher×talk_to_the_cityでplurality本の内容を可視化×bertopic×bertopic:_neural_topic_modeling_with_a_class-based_tf-idf×umap×hdbscan×mashbean×初探_polis_2.0:邁向關鍵評論網絡×熟議×レジリエンス×双方向的マスコミュニケーション×国民ラジオ×一方向的マスコミュニケーション×聞く姿勢×デジタルネイティブは4年に1度のアップロード帯域で十分とは思わない×雪玉×polis_2.0×発想法×川喜田二郎×kj法×凝集型階層的クラスタリング×u理論→

- →Polis×vTaiwan×audrey_tang×g0v×Colin Megill×polis:_scaling_deliberation_by_mapping_high_dimensional_opinion_spaces→
- →収益性×社会的意思決定×税金×csr×ローンディール×受益者×verifiable_credentials×分散型id×acount_abstruction×DeCartography×Polis×plurality×gitcoin×psycho-pass×哲人政治×達成できたら解散×子孫から借りている×互恵的関係×移動式投票×土地に結びついたコミュニティには抜けにくさがある×逆インセンティブ→
- →日記2024-05-11×シンギュラリティ×空気抵抗×社会を均質なもので近似する誤謬×広がりのあるものを点で近似する×同じものに属する違うもの×イコールでないものを同一視し、差の拡大によって同一視できなくなる×引き伸ばし×引き裂かれ×世界のちぎれ×つなぐビジネス×未然に防ぐより壊れてから直す×津波が来る場所に立ち止まらない×津波てんでんこ×理解する能力×誰がカモかわからない人がカモ×落ちこぼれ×伸びこぼし×底上げが必要か?×トップを伸ばす×アーリーアダプター集団の形成×コスト構造の変化×人生の時間→
- →政治哲学×パナーキー×民主主義×競争性×二大政党×無意味な選挙×シルバー民主主義×リモートワーク×自治体×バーチャル化×デジタル化×移動のコスト×移動式投票×ド・ピュイド×政府間競争×機能的重複競合管轄権×マルチ・ガバメント×アナーキー・国家・ユートピア×メタ・ユートピア×なめら会議4×rickshinmi×汎統治主義×自由競争×レッセフェール×政府の不介入×競争原理×革命×暴力的な政変×個人の自由×多様性×政府のサービス向上×政府の効率化×社会制度をフォークする→
- →Quadratic Voting×plural_management_protocol×サイボウズラボ勉強会×Plural Management勉強会×plural_management×Quadratic Voting: How Mechanism Design Can Radicalize Democracy×quadratic_funding×liberal_radicalism:_a_flexible_design_for_philanthropic_matching_funds×メカニズムデザイン×メカニズムデザイン勉強会×majority_judgement勉強会×一人一票が不自然×坂井_豊貴×ラディカル・マーケット×eric_a._posner×e._glen_weyl×謙虚さ×個人主義×リッカート調査×民主主義×quadratic_votingはなぜ平方根を取るのか×nash_equilbria_for_quadratic_voting×ベイジアンナッシュ均衡×一人一票×多数派の専制×アレクシ・ド・トクヴィル×彼らが最初共産主義者を攻撃したとき×マルテイン・ニーメラー×心を動かす×液体民主主義×democracy_earth×radicalxchange×join×過度の一般化×preference_voting×ranked_voting×選好順序×継続価値×発言権クレジット×qvは投票しないことに意味のあるメカニズム×vitalik×gitcoin×gov4git×pluralitybook×共有地の悲劇×慈悲深い独裁者×アジェンダ設定の権限を人々に開放する×トークンエコノミー→
- →steven_lalley×e._glen_weyl×Quadratic Voting×mechanism_design×メカニズムデザイン×民主主義×平方投票×直接民主制×発言権トークン×アテンション×継続価値×発言権クレジット×quadratic_votingはなぜ平方根を取るのか×中庸→
- →日記2024-01-20×幸福な統治×情報収集手段×人間より賢いai×同じ入力が与えられたなら×人間の中央値より賢い×幸福×統治×帯域×選挙は4年に一度5bit送信する遅い通信だ×メカニズムデザイン×Quadratic Voting×多数決という貧弱なアルゴリズム→
- →plurality×audrey_tang×e._glen_weyl×テクノロジーと民主主義は戦争状態×反民主的なテクノロジー×aiは反民主的なテクノロジー×chatgpt×言語モデル×実存的リスク×シンギュラリティ×アシスタント人工知能×変革的技術×人間社会に不可逆な影響を与える×独裁国家×協調的多様性×collaborative_diversity×協働できる多様性×democratic_inputs_to_ai×民主的プロセス×意思決定×少数の人間×公共の利益×多様な視点×概念実証×チーム×よりグローバルで、より野心的なプロセスの基礎×新たな民主的ツール×aiの未来のための試み×code_for_japan×code_for_nagoya×創設メンバー紹介×地球規模の熟議×反復構造×日本文化ai×異文化理解×ドラえもん×sf×aiは友達×付喪神×神×サピア=ウォーフの仮説×思考の部品×取っ手×名前×民主的プロセスとはなるべく多くの人の納得感を生み出すプロセスだ×納得感×plural_thinking×omoikane_vector_search×minimum_viable_product×大きなストーリーの一部になる×参加証明nft×貢献証明nft×hypercerts×retrospective_funding×halsk×mmotrpg×オープンベータ×採否は未定×熟議の方法論×プロジェクトに参加する→

- →機械翻訳は誤訳する、gptは誤訳だけでなくハルシネーションする×ai独裁制×独裁制×デジタル民主主義×日記2023-12-17×日記2023-12-19×日記2023-09-09×日記2022-12-18→
- →plurality×cybozu×collaboration×diversity×technology_for_diverse_individuals_to_work_together_to_accomplish_things×building_a_society_brimming_with_teamwork×teamwork×100_people,_100_ways×empathy×empathy_towards_ideals×broad_listening×not_subjective_or_objective,_but_from_one_subjectivity_to_many_subjectivities×Polis×vTaiwan×groupware_as_media×productivity_improvement_software×social_media×work_together_to_achieve_common_goals×adapt_to_change×pro-social_media×groupware×digital_democracy×understood_and_implemented×agenda_setting×Pluralityとサイボウズ(2023)→
- →投票率×forkできないものを動かすのが政治×いい公共財×表象×DeCartography×投票で何を動かすか?×tvl×forkできるもの(dao)で投票する際に何を動かしているかというと、アセットの流動性が限りなく高いのであればtvlのみになる。移動式投票とかに近い→
- →plurality×経験から浮かび上がるまだ名前のない概念×経験の言語的な伝達は情報量が不足しがち×フォーカシング×考える花火×ポランニーの暗黙知×共同化×体験過程×思考の結節点2023-04-10午後×the_implicit×日記2023-08-25×ユージン・ジェンドリン×川喜田二郎×環境の変化が速くなると知識ではなく知性が信頼される→
- →村×ソリディティ村×民主主義×メイフラワー号×ピューリタン×社会契約×プリマス植民地×アレクシ・ド・トクヴィル×リテラシー×アーリーアダプター×小さなコミュニティ×合意形成×社会の仕組み×ゲーテッドコミュニティ×村社会2.0×落合_渉悟×鈴木_健→
- →主観か客観かではなく、一人の主観から大勢の主観へ×エンジニアの知的生産術×plurality×熟議のための4つのステップ×Polis×PluralityとPolis勉強会×世界とaiのインターフェース×正統性×移動式投票×Panarchy×arxiv→
- →plurality×Polis×サイボウズラボ勉強会×階層組織×LLMがもたらす組織構造の変化×ダンバー数×国民ラジオ×松下幸之助×サイロ化×llm×audrey_tang×ブロードリスニング×人間の増強×知識社会は上司と部下の社会ではない×階層的な組織よりも水平的な組織の方が容易になる×統治構造×選挙は4年に一度5bit送信する遅い通信だ×vTaiwan×チームワークあふれる社会を創る×技術は中立×善用×悪用×パノプティコン×監視×社会信用システム×フェイクニュース×画像認識×雨傘運動×シンギュラリティ×broad_listening×decentralized_id×quadratic_funding×retroactive_funding×ソーシャルインパクトボンド×Quadratic Voting×decentralized_identifiers×gitcoin_passport×worldcoin×web3はオワコン×終わったように見えるのは流行の上振れしか見えてないから×共感×異文化理解力×意思決定×合意形成×空気が支配する日本ではブロードリスニングが重要×human_augmentation×when_we_hear_“the_singularity_is_near”,_let_us_remember:_the_plurality_is_here×roulette_wheel_selection×t-sne×polis:_scaling_deliberation_by_mapping_high_dimensional_opinion_spaces×polis勉強会×都市国家×デジタルネイティブは4年に1度のアップロード帯域で十分とは思わない×紙と箱による民主主義×デジタル投票×アジェンダ設定の権限を人々に開放する×シルバー民主主義×一人一票×論点のブレインストーミング→
- →democratic_inputs_to_ai×熟議×代議制×議会制民主主義×自分の声が届いていると感じること×自分の声×真っ向から意見が対立しても合意できる×PluralityとPolis勉強会×アップロード速度×平等な個人による参加と責任のシステム×諦め×諦感×無力感×前提知識を踏まえていない×意見を投げる前に学ぶことが必要×学びが足りていない×前提知識の共有×民主主義×議会制×民主制×共和制→
- →desci×分散型サイエンス×公共性×パブリックブロックチェーン×web3×濱田_太陽×研究資金調達のオルタナティブをめぐって×web3とweb3.0は別物×ヴィタリック・ブテリン×the_most_important_scarce_resource_is_legitimacy×gitcoin×イーサリアム×エコシステム×分散型金融×1inch×国際連合児童基金×unicef×パーミッションレス×反競争性×anti-rivalry×メカニズムデザイン→
- →stanford_online_deliberation_platform×時差のあるイベントの日程確認×Polis×prebunking×討論型世論調査×TRUTH, TRUST AND HOPE×better_online_conversations_with_automated_moderation×モデレーションの自動化×pol.is×deliberative→
- →民主主義×フェイクニュース×間主観×合意形成×真実の共有×現実の共有×真実×ポスト真実×「より多くの意見を認める」と「すべての意見を認める」は違う×遅いシステムの移行先としてのdapps×スパラクーア×刺激洪水×思索×書き留め×熱意を破壊する行為には社会的ペナルティを与えた方が良い×新大陸が発見されても全員は移住しない×日記2023-05-13×日記2023-05-15×日記2023-02-03×日記2022-05-14→

- →horizontal_organisation×audrey_tang×democracy_needs_to_evolve_into_a_real-time_system×階層組織×LLMがもたらす組織構造の変化×PluralityとPolis勉強会×broad_listening×水平組織×知識社会は上司と部下の社会ではない→
- →解雇規制×雇用需要の減少×転職市場の悪化×雇用需要×早期退職×中間管理職×aiとの競争×aiを使いこなせる人間×介護×人手不足×中山_心太×サム・アルトマン×ユニバーサル・ベーシック・インカム×メンバーシップ型雇用×企業内ベーシックインカム×ジョブ型雇用×倒産×LLMがもたらす組織構造の変化→
- →シンギュラリティ×プルーラリティ×対立構図×誤った二項対立×誤った二分法×観測範囲×同じ本質的な存在を異なる視点から解釈している×ai独裁制×止揚×自分たちがハンドルを握っている×我々が我々の主人×物理的身体を持ったセンサーノード×判断×360度の視角から→

- →plurality×表層の政治より統治の政治×政治思想×統治技術×ミシェルフーコー×統治性×カント×永久平和のために×非中央集権×ルソー×社会契約論×一般意志×dividual×分人×スケールフリーネットワーク×優先的選択×デリダ×誤配×1person_1vote×Quadratic Voting×なめらかな×委譲×RxC Voice×定言命法の倫理×quadratic_funding×gitcoin×plural_qf×social_diversity×コーディネーションゲーム×集団的知性×Polis×vTaiwan×picsy×science_of_science×scisci×desci_tokyo×stigmergy×創発×social_bookmark×sensemaker×optimize_by_attention→

- →aiのための作業の対価を暗号通貨にする×納税×semantic_annotation×proof_of_human×まだ書かれていないことの森を切り拓いていく仕事×ベーシックインカム×現代貨幣理論×表券主義×DeCartography×ユニバーサルベーシックインカム→

- →遊牧民×移動する人×定住する人×遊牧×隊商×交易×貿易商×(7.2.5)_組織の境界をまたぐ知識の貿易商戦略×移動が観測範囲を広げる×観測範囲×孤立×むすびつけ×ネットワーク化×移動×定住×人生の選択肢×選択肢×知識を運ぶ×知識の貿易商×認知・選択格差×移動することで初めて見える×来訪者×変なやつ×まれびと×差分にしか意味は宿らない×DeCartography×gitcoin×一般意志の可視化×アルゴリズム型民主主義×permissionless×quadratic_funding→
- →ゲーム理論×岡田_章×戦略形ゲーム×ナッシュ均衡点×展開形ゲーム×完全均衡点×情報不完備ゲーム×繰り返しゲーム×期待効用理論×サンクトペテルブルクのパラドックス×アレのパラドックス×2人交渉問題×コアの理論×コア(ゲーム理論)×協力ゲーム解×シャープレイ値×n人提携交渉問題×社会的選択×メカニズムデザイン×アローの定理×戦略的操作可能性×進化ゲーム→
- →タスク×ふせん×川喜田二郎×フェーズ×知識×あなた×サイクル×読み方×メタファ×本章×優先順位付け×kj法×全体像×しくみ×抽象化×プログラミング×やる気×ピラミッド×ソフトウェア×注×プログラム×whole_mind_system×パターン×プログラミング言語×ボトムアップ×たとえ話×価値×プロセス×知的生産術×分野×概念×アウトプット×グループ×学び×目的×他人×言語化×海馬×情報×考え方×誰か×視点×創造性×書き出し法×速度×盲点×教科書×原動力×方法×アナロジー×表札×発想法×方法論×それ自体×抜き書き×incremental_reading×単語×抽象概念×情報収集×見積り×一覧性×著者×文章×意思決定×シナプス×脳内×インプット×記憶×ルール×暗黙知×ゴール×写経×ソースコード×モデル×仮説×顧客×コンピュータ×実験×エンジニア×グラデーション×モデル化×アジャイル×supermemo×速読術×言葉×自分×複数×ボトルネック×ラット×複数人×フィードバック×具体例×symbolic_modelling×書籍×何回か×コーディング×岩波書店×メリット×レポート→
"Engineer's way of creating knowledge" the English version of my book is now available on [Engineer's way of creating knowledge]

(C)NISHIO Hirokazu / Converted from [Scrapbox] at [Edit]