どう作るかではなく何を作るかが大事
from 日記2025-10-18
どう作るかではなく何を作るかが大事
>nimdanaoto 実際この認識で, 技術力は教育でなんとかなるので, アイデアを持ってる人間に技術力つけさせて成功させようというプロジェクトだと思っている
> 私も未踏やる前はC++をstdout付きのCとして書いてるレベルの人間だったし暗号もAESとRSAしか知らなかったからなぁ
> >_kokt_vrc: 未踏、技術力のある人間を掘り出すのではなくてアイデアを持っている人の実現を支援しているだけにしか見えないと言ったら言い方が悪いけど、アイデアはないけど技術力はあるみたいな人が対象になってない
>nimdanaoto 力を持つことより力を正しく振るうことのほうが難しいがち
なんらかの技術を持ってる人がアイデアや熱意のないときに、メンターがアイデアを与えたら、それはメンターの下請けにすぎない
アイデアがあることは技術力云々の前段階の必要条件
"アイデアはないけど技術力はある"という表現はアイデアを軽視している
アイデアを「思いつくもの」かのように思っていると思う
つまり技術力が低い
すでに自分が獲得している技術だけを技術だと考える視野狭窄に陥っている
価値を感じていないものを学ぶことは困難なので、すなわち「育成困難な個体」ということになるから
Related Pages
- →サイボウズラボ勉強会×plurality_in_japan(サイボウズラボ)×funding_the_commons_tokyo_2024×talk_to_the_city勉強会×tttc:_aiと著作権に関するパブリックコメント×サイボウズと語ろうplurality_多元性の実践と期待×2024-09-08-民主主義を支える技術×ブロードリスニング×meetup_with_thomas_hardjono×ソーシャル物理学×テクノロジーとわたしたちの「距離感」が変われば、誰も取り残されない社会がつくれるかもしれない×デジタル民主主義×ブロードリスニングの「あの図」×階層組織×ティール組織×個人情報とマネタイズ×成蹊大学×2019年度武蔵野市寄付講座「itとルールの今・未来」×計画経済×llmがもたらす組織構造の変化×ブラウン組織×plurality_tokyo×pluralityとpolis勉強会×主観か客観かではなく、一人の主観から大勢の主観へ×情報の複製により情報発信は効率化されたが、受信は改善しない、情報を減らす技術が必要×関_治之×激動の2024年5月下旬×ミーム化×asia_blockchain_summit_2024×サイロ化×組織の境界×なめらか化×plurality_in_japan×良い議論ができる場を可視化の後につける×可視化×aiあんの×u理論×ソーシャルフィールドを耕す×mashbean×dx&ai_forum_2024×生成aiで作るデジタル民主主義の未来×「聴く」「磨く」「伝える」のサイクル×human_in_the_loop×people_in_the_loop×オモイカネ勉強会×chatgptとaiあんののコミュニケーションの形の違い×社会的学習×アイデアの流れを混ぜてアイデアの多様性を増す×組織としての学習×集団的知性×複数組織とブロードリスニング×個人的文脈×当事者意識×ファウンダーマーケットフィット×熱意×proj-broadlistening×social_hack_day→
- →アイデア×勇気×がむしゃら×盛田_昭夫×ソニー×アイデアに着手する勇気×うまくいかなかったときに自分の行動の何かが悪いと認める勇気×一度失敗したことに再チャレンジする勇気×何度も失敗しても成功するまで時間を投資する勇気×たくさん時間を使ってきたことを失敗だと判断して辞める勇気×コンコルド効果×時間の投資×魔改造の夜→
- →課題感と解ける課題×プロジェクト発生成長のプロセス×繰り返し会う×適度なサイズの課題×明確に言語化された課題×よい課題×熱意×優れた人はアイデアを語る×ぼんやりとした課題感×共感×自分ごと化×集まるのが最初の一歩、一緒に居続けるのが進歩、一緒に働くのが成功×現金は弱い資本×稀少な資源×調達困難リソース×強者はますます強く×pdcaサイクル×u曲線モデル×社会実装×協働プロジェクト×コラボレーションハブ×みんな個人プロジェクトを持ってる×未踏人材の間の接続×ネットワーク形成システムとしての未踏×つなぎ合わせる×経済的価値×社会的価値×「未踏ジュニア」はどのようにプロジェクト化されたのか→
- →老×老人×老害×老害化×暇×暇人×暇害×暇害化×アヘン×何かを作り上げることに熱意を持って取り組んでる人は忙しくしてる×産みの苦しみ×苦しみ×熱意×ものづくり×小人閑居×暇なときに魔が差す×苦味×アフォガード×熱狂できずに諦めた自分を守るための嫉妬→
- →起点×アイデア×自分の頭で考えることができる人×他人の考えから影響を受ける人×菊地敦己×領域を横断×平野敬子×文章が作られるプロセス×最初に置かれるべきものは半ばで出てくる×文章は順繰りに生まれるのではない→
- →未踏事業×quadratic_voting×伴走×合意形成メカニズム×熱意×個人と密結合×quadratic_funding×和で評価するとジェネラリストが選ばれる×尖った人材を取るためには順位の調和平均×社会的手抜き×直接のマッチングが人的ネットワーク形成に重要×人的ネットワーク形成システム×目利きの目利き→
- →真鶴2023-05-13×課題感×解ける課題×プロジェクト発生成長のプロセス×解く手段×技術×マッチング×ニーズシーズマッチング×現金というコモディティ×お金で買えないリソース×理解×熱意×言語化×ブレインストーミング×自信×自己肯定感×polis×匿名シードコメント×課題感と解ける課題→

- →未踏ジュニア×子どもの創造性を喚起するサード・プレイス×未踏カルチャー×カルチャー×pm制度×自発的×自発性×内発的動機×熱意×自力で前に進む力×自走力×ファーストペンギン×自分ごと感×圧倒的当事者意識×coderdojo×coderdojo憲章×事後的リーダーシップ×イノベーティブな人材を事前に目利きできるか?×自分志向→
- →アイデア×発想法×デール_・カーネギー×your_creative_power×オズボーンのチェックリスト×ブレインストーミング×alex_osborn×すべてのアイデアの記録×発明とは一時に完全な形で現れるものではない→
- →アヴァロン×ヤバイ組織×ボードゲームコネクトキャンプ2017×エセ芸術家ニューヨークへ行く×レジスタンス:アヴァロン×人狼×ソーシャルブックマーク×ストローク×強化×hook_model×面白くない人×xについて言語化できないときに「逆にnot_xはどんなもの?」と聞く×認知の狂い×利他ではなく長期投資×人格と意見は別物×トーンポリシング×突破する個人×自発性×熱意×誤った二分法×何か変化はありましたか?×抽象概念×次に何が起こる×少し前には何が起こる→
- →熱意×熱意は希少なリソース×やりたい×問題を解決したい人と仮説を検証したい人×作りたいのではなく中身を知りたい×思考の結節点2021未踏ジュニア×手段xで問題yを解決して顧客zを幸せにする×学習性無力感×まず自分のニーズを満たすものを作れ×顧客不在→
- →eleanor_roosevelt×great_men_talk_about_ideas×凄い人はアイデアの話をし、しょぼい人は他人の話をする×アイデア×ゴシップ×mediocre_men_talk_about_things×small_men_talk_about_people×素晴らしい人はアイデアを語る×優れた人はアイデアを語る×個人攻撃→
- →技術評論社×コーディングを支える技術×理解を確認するためにはまずアウトプット×何を学べばよいかがわからない理由×具体的な知識と抽象的な知識×噛み砕く×必要なところからかじる×おおまかにつかんで徐々に詳細化する×端から順番に写経する×効率的に学ぶには×知識の3つの軸×学びの3つのフェーズ×最初の一歩をどう踏み出すか×必要なところを学ぶ×全体像をつかむ×写経する×どうやって深く理解するか×比較×歴史から学ぶ×作って学ぶ×何を学ぶか×何を作るか×問題の探し方×成果の出し方×言語を深く効率的に学ぶには×エンジニア×学び方×知識×成果×2014×04-24×2014-04→
- →正解×サイクル×学びのサイクル×やる気×タスク管理×記憶×間隔反復法×本を読む×速読×知識ネットワーク×まとめる×川喜田_二郎×kj法×アイデア×アイデアを思い付く×理解を深める×パターンを発見する×新結合×エンジニアの知的生産術_著者公式ページ→
- →京大サマーデザインスクール2014×学び方のデザイン×ブレインストーミング×学び方×知識の結合×kj法×結論厳禁×自由奔放×質より量×結合改善×アイデア×問題の提示×創造力を生かす×すべてのアイデアの記録×発想する会社×思考の整理学×凡才の集団は孤高の天才に勝る×ブレインライティング×computer_brainstorms×組織とグループウェア×クラウドストーミング×groups:_interaction_and_performance→
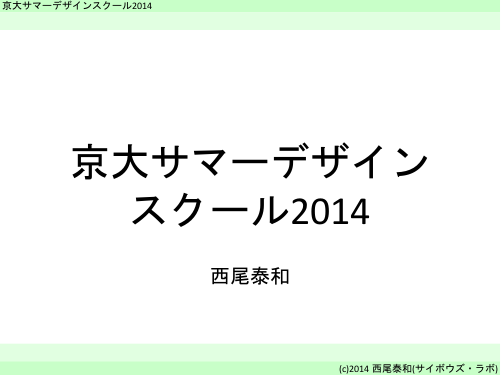
"Engineer's way of creating knowledge" the English version of my book is now available on [Engineer's way of creating knowledge]

(C)NISHIO Hirokazu / Converted from [Scrapbox] at [Edit]
