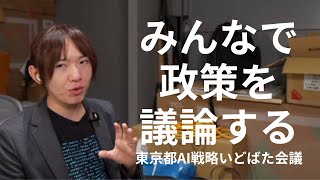共同体志向と目的志向の二重組織
目的志向の組織からは目的の達成に寄与しないメンバーは排除されるべき
共同体志向の組織はメンバーを排除しない
仲良くすることが求められる
この二つの「組織の存在意義」は両立しない
共同体志向の広い組織を維持する
そこに集まった人の中から有志が目的志向のプロジェクトチームを結成する
同窓会組織なるものは、参加条件がgivenである
なので参加条件を満たす人を排除する選択肢はない
よって共同体志向しか選択しえない
参加条件が存在するのでゲーテッドコミュニティである
プロジェクトチームは意思決定の速度を考えると少人数であるべき
「最大7人」ぐらいのイメージ
いちいちチーム外のメンバーの許諾や承認を求めてはいけない
一方、活動がチーム外のメンバーに共有されないと不満が起きる
あずかり知らないところで物事が決められている
意思決定を事後的に共有し、フィードバックを返すという関与の機会を作る
自発的に意見とsweatを出す人なら事後的にチームに追加する手もある
これは二重組織と正統的周辺参加だ
Related Pages
- →時間軸の構造を破壊×時間軸構造の破壊×ティアキンの祠×仕事のゲーミフィケーション×ピラミッドの頂上を取ってきても期待と違う×抽象を軸足にした変換×銀の弾などない×肥満の解消には運動するといい×打席に立つ回数を増やす×mvp×pdcaサイクル×耳にタコができるくらい聞くのは、本当にそれが真理であるから×構想力は問題を限定する能力×二重組織×調達困難リソース×移転可能×移転不能リソース×熱意は貴重なリソース×知識のネットワークがあると高速移動ができる×人間ベクトル検索エンジン×成長欲求×物理的身体×組織境界の曖昧化×なめらか化×ランダマイザ×グラフィカル思考×指数的成長の後押し×新しいs字曲線に投資した方が得×雪崩×峠を越えると指数関数的成長×参入障壁×ブラックボックス×社会資本での拡大再生産×社会関係資本の使い方×貿易商×巻き込み力×巻き込まれ×巻き込まれ力×都合よく使われることのメリット×自発性と巻き込まれ力×面白い×意外性×盲点×サイクルを閉じる×盲点カード候補×連想のストック×誤ったkpi設定×「ぶどう園の労働者のたとえ」と「悪人正機説」の関係×情熱×専門性×博士号×the_illustrated_guide_to_a_ph.d.×高次元空間におけるトゲトゲ×シリアルマスタリー×シリアルマスタリーはバーベル戦略×実弾×使えるカード×他人が容易に獲得できないリソース×市場調達できないリソース×活動履歴は市場調達困難な財×転がる雪玉×過冷却のメタファー×新結合と水面のたとえ×connecting_the_dots×決断の機会は数珠つなぎ×retrospective×エフェクチュエーション→
- →コミュニティ×プロジェクト×ゲゼルシャフト×ゲマインシャフト×明確なリーダーの存在×n対nコミュニケーションチャンネル×リーダーシップ×多様なつながり×コミュニティ運営×プロジェクトの束としてのコミュニティ×社交的つながり×具体的な成果×短命なコミュニティ×銀座マダミス会×小さくて時間限定で消滅する短命なコミュニティを生み出す×持続的なコミュニティ×運用を楽しむ×反復的なプロジェクト→
- →scrapboxで相互理解を深める×二重コミュニティ×ネットワーク形成システムとしての未踏×囚人のジレンマに耐性のあるコミュニティ構造×ポッセ×非営利組織の経営×2020未踏社団:プロジェクト発生成長のプロセス×実践共同体×関心共同体×越境的学習のメカニズム×友達×組織×共同体×ゲゼルシャフトとゲマインシャフト→
- →フェルディナント・テンニース×組織には2種類ある×ゲマインシャフト×gemeinschaft×共同体×共同体社会×地縁×血縁×友情×人間関係×メンバーの快適×ゲゼルシャフト×gesellschaft×機能体×利益社会×共通の目的×共通の利益×達成×目的の達成×テンニース×近代化×組織論×会社組織×従業員満足度×働きやすい環境づくり×従業員クラブ活動×誤った二分法×企業の大家族化×ティール組織×2種類ある→
- →見慣れないものをちゃんと見ずに攻撃する×観測範囲の問題×世の中の大部分のものは人間が関わっている×壁を作る×接触の機会×ゲーテッドコミュニティ×散弾銃×可能性の扉×けなす人の世界は閉じていく×あいまいな言葉は散弾銃×散弾銃で攻撃して報復される×狂犬×君子危うきに近寄らず×争いは同じレベルの者同士でしか発生しない×1人当たり1秒もない×攻撃は生産性を下げる×暴言は生産性を下げる→
- →バザールとクラブ2024-02-14×バザールとクラブ×ギアツ×ローティ×心理的安全性×shared_belief×多様性の使いどころ×エスノセントリズム×「エスノセントリズムに陥るなら死んだ方がマシだ」という思考がエスノセントリズム×ブルジョワ・リベラル×惰弱なリベラル×反エスノセントリズムの帰結×自尊心の崩壊×ユネスコ的コスモポリタニズムの絶望的な寛容×反-反エスノセントリズム×コスモポリタニズム×コミュニティ×手続的正義×ほとんど窓のないモナド×よいどれ×わかる必要はない×手続き的正義×ロールズ×正義論×手続的正義中心の社会×the_most_important_scarce_resource_is_legitimacy×プロセスによる正統性×エンゲルス×自然の弁証法×イギリスにおける労働階級の状態×ポストモダン×ブルジョワリベラル×啓蒙主義×人間本性×諸権利×基礎構造×上部構造×文化的×特定の文化的偏見×自己言及のパラドックス×「合理的」と「文化的」の間に境界がある前提×平等は西洋の奇習×デューイ×リベラルな寛容の限界×pbl×必然と考えられてきたものの偶然性×クワイン×ウィトゲンシュタイン×デリダ×自分の中心と周辺を区別することば×アイデンティティ×どこから来たのか×偶然的な時間空間的所属×なめらか×合理性についての合理論的理論×バーナード・ウィリアムズ×人間の平等×局所的文化×クラブが異なっていてもよい×相手のクラブのメンバーである必要はない×プラグマティックなリベラル諸制度×利点を挙げるだけでよい×多様性は単に無視されるべきもの×クラブに取り囲まれたバザール×共同体×ゲマインシャフト×価値観を共有した共同体に所属しないまま、手続的正義によって動く市民社会に所属することができる×リベラルのけいれん×クラブは善の構想を共有する×善悪と無関係の手続的正義が支配する×クラブの排他性×世界秩序×嫌悪感×道徳的ナルシシズム×啓蒙主義への裏切り×排他性が私的な自意識の必要条件×バザールの維持×自文化中心主義でも協力できる×ロールズ流の手続的正義へのコミットメントが市民権の要件×コミットメントは道徳的ではなく便宜的でありえる×公的なプラグマティズム→
- →斧を研ぐ暇がない×limitless_ai_pendant×cosenseaibooster×パーミッションレス×目的志向組織×二重組織×日記2025-06-08×日記2025-06-10×日記2025-03-01×日記2024-06-09→

- →鈴木健×tbs_cross_dig_with_bloomberg×分断×民主主義の機能不全×複数の所属×セミラチス×二値的な線引き×組織境界の曖昧化×二重組織×認知限界×なめらかな社会×アメリカで内戦が起こると考える人が多数派×リニアな問題解決とサーキュラーな問題解決×問題と偽解決の悪循環×逆張り×メタ認知×人間中心主義×aiが投票権を与える×猿の惑星×pluralityとは×why_i_am_not_a_market_radical×安野チーム台湾報告会×個人主義×国家中心主義×脱近代×終わるのではなく層が重なる×個人メディア×picsy×欲望の二重の一致×生命ネットワーク×複雑な世界観を実装していく→

- →aiエージェントのマネジメント×pmbok×スコープ定義×目的×期待する成果×スコープの明確化×役割×役割の明確化×コミュニケーション計画×情報共有×リソース管理×ステークホルダー×利用者の要件×ステークホルダー管理×統合変更管理→
- →批判的な分析の背景にある羨望や不安×ゲマインシャフト×コミュニティ×観察対象×観察者バイアス×参加型観察×参加観察×参与観察×観察対象化×クリフォード・ギアツ×厚い記述×エドワード・サイード×オリエンタリズム×異なる存在×自分自身を優位に置く姿勢×エヴェレット・ヒューズ×アウトサイダーとしての視点×エスノメソドロジー×会話分析×「観察」そのものが現実を再構成する行為×疎外感×他者理解×一員としての関係性→
- →利己主義×エゴイズム×アイン・ランド×コーディネーション×自分の利益を目的とした行為は悪である×奴隷道徳×力のある者が利益を得る×逆張りの価値観×自己中×美徳×利己的×利他主義×誤った二者択一×客観主義×啓蒙思想×アメリカ建国×国が諸君に何をしてくれるかを問うな。諸君が国に対して何をできるかを問え×二月革命×十月革命×ウラジーミル・レーニン×ボリシェヴィキ×クリミア×夜警国家×真善美×プラグマティズム×利他ではなく長期投資×リバタリアニズム×アダム・スミス×原子論的×個人主義×マルクス主義×カール・マルクス×フリードリヒ・エンゲルス×市場経済モデル×社会的協力×共同体×円キャリートレード→
- →コミュ力×2種類ある×キッカケを作るタイプ×キッカケ×交通整理が上手いタイプ×交通整理×コンフリクトの解消こそが共同体を形成していく×葛藤×ゲマインシャフト×きっかけを作る×0→1×突破力×きっかけ×メンテナンス×混乱の解消×問題の解決×コミュニケーション力×雑な発言×巻き込み力×kawahii→
- →エフェクチュエーション×起業家的熟達×非予測的コントロール×手中の鳥×目的主導×goal-driven×手段主導×means-driven×目的×手段×許容可能な損失×期待利益×許容可能損失×バーベル戦略×クレイジーキルト×機会コスト×競合分析×コミット×erin_meyer×レモネード×飛行機の中のパイロット×技術トラジェクトリ×トレンド×人間に働きかけることが事業機会創造の主たる原動力×コントロールできないことは気にしない×計画的偶発性×セレンディピティ×事業計画×利用可能なリソース×手駒を見る×bird_in_hand_principle×現在持っているリソース×誰を知っているか×何を知っているか×誰が自分を知っているか×明確な目標がなくとも行動を開始する×許容可能な損失を考える×affordable_loss_principle×潜在的なリターン×レモネードの原則×lemonade_principle×パッチワークキルトの原則×patchwork_quilt_principle×パイロット・イン・ザ・プレーンの原則×pilot_in_the_plane_principle→
- →正統的×周辺×参加×legitimate×peripheral×participation×「学び」は社会的行為×学び×授業的イメージ×知識の流れが一方通行×徒弟制×能動的×主体的×フィードバック×正統的参加×周辺参加×自発的×二重組織×u理論×2015→
- →実践共同体×作る人×社会を実装する人×実装×私たちは政治システムをコーディングすることができます×実装なき思想はもういらない×シグナル×社会の再構築×シグナリング×応援する人をまとめる×既存の枠組み×インナーサークル×二重組織×取りこぼさない×なるべく取りこぼさない×デジタル民主主義×都知事選ハッカソン×「なぜ誰もやらない」と言うな、あなたもその一人だ×安野たかひろ×ブロードリスニング×plurality×熟議民主主義×polis×tokyoai×安野たかひろを都知事に×5000万円の選挙資金×日記2024-06-27×日記2024-06-29×日記2024-03-20×日記2023-06-28→
- →日記2024-04-03×llmとは電磁気そのもの×イノベーション化×シニフィエ×綱引きがゴンゴン変わっていく×ゲゼルシャフトは梯子外し率が上がる×ゲゼルシャフト×フェルディナント・テンニース×梯子外し率が上がる×ゲマインシャフトがより安牌になる×ゲマインシャフト×避難所×shogochiai2/8×shogochiai3/1→
- →2018-03×エンジニアのための自分経営戦略_参考文献×"エンジニアのための自分経営戦略"まとめ×陳腐化×if文から機械学習への道×きこりのたとえ×旅人×7つの習慣×新しいこと×不安×損失額の限定×リアルオプション×経営戦略×リソース配分×資源配分×戦略サファリ×スモールスタート×列挙を疑え×お金は使うとなくなる×ポスト資本主義社会×知識獲得戦略×行動×環境×結果×実験×pdcaサイクル×リーン・スタートアップ×知識の交換によって学ぶ×知識が双方向に流れる×知識の少ない人からでも学ぶことができる×知識交換の必要条件×周りと同じものを学んでも知識交換はできない×知識の分布図×競争優位×マイケル・ポーター×ファイブフォース分析×狭き門×市場開拓コスト×状況×状況に埋め込まれた学習×ゲーテッドコミュニティ×共有地の悲劇×二重コミュニティ×答えをコピーしても無益×連続スペシャリスト×π型人材×技術進歩による海面上昇×言葉が熟す×アウトプットを焦ると劣化コピーになる×giver→
- →アジャイルな執筆プロセス×ペアマッハ新書×箇条書き×マッハ新書×共同編集×mvp×ゲーテッドコミュニティ×scrapbox×書き出し法×破壊的イノベーション×時間同期的×時間拘束的×書き散らした原稿を整理する×doneの定義が不明瞭×レベニューシェア×ペアプログラミング×ペア×第三者の眼×教育×執筆×google_docs×yoshifumi_yamaguchi×アポ取りがめんどくさい問題×付加価値×facebookグループ→
- →意思決定×チーム×必要だと感じたことを何でもやっていく×コンセンサスを得ようとしない×スタンドプレーから生じるチームワーク×良いアイデアなら許可を求めるな×コンセンサス×タックマンモデルのstorming→
- →それぞれがエンジンを着ける×技術的実力行使×実力行使×まずやって、それから調整×ポジションを取った後に批評しろ×結果が出てから評価する方が楽×良いアイデアなら許可を求めるな×良いアイデアは周囲の人を刺激し、自分で成長を始める×ムーブメントはフォロワーが作る×未踏ジュニアscrapbox×オモイカネプロジェクト×危機感は言葉でシェアできない×津波てんでんこ×タイタニック×舵取り×ソフトランディング×離脱・発言・忠誠×組織効力感×ゲリラ戦×plurality_tokyo_salon_2023-07-08×日記2023-07-06×日記2023-07-08×日記2023-03-29×日記2022-07-07→
- →村×ソリディティ村×民主主義×メイフラワー号×ピューリタン×社会契約×プリマス植民地×アレクシ・ド・トクヴィル×リテラシー×アーリーアダプター×小さなコミュニティ×合意形成×社会の仕組み×ゲーテッドコミュニティ×村社会2.0×落合_渉悟×鈴木_健→
- →フォーク定理×均衡選択×主人と奴隷×まだ絵のない盲点カード×互恵的×利己的×ゲーテッドコミュニティ×囚人のジレンマとコミュニティの観察者×コミュニティによる生産性向上のすすめ×互恵的な行動をする人と利己的な人を見分ける方法×観察者を置くことによる囚人のジレンマの破壊×利己的な人を効率よく排除する方法→
- →aiボット×役割×目的×エンジニアの知的生産術×書籍としてのエンジニアの知的生産術×scrapbox上のコミュニケーションの場としてのエンジニアの知的生産術×aiと人間の参加する場としてのエンジニアの知的生産術×incremental_reading×scrapboxをもっと活用する案×再度発散フェーズ×発散フェーズ×AIの役割の明確化が大事×omoikane_bot×memochat→
- →タックマンモデル×storming×tuckmanのチーム開発モデル×bruce_tuckman×チーム×対立×目的×役割×リーダーシップ×不確実性×信頼×開かれたコミュニケーション×感情の表現×対立解決→
- →キャンプファイヤー×組織に明確な境界はない×中央×ビジョン×距離感×人の輪×真ん中で踊り続ける×おもしろい×ゲーテッドコミュニティ×組織境界の曖昧化×二重コミュニティ×ビジョンはおもしろいのが重要×人の輪が広がる×人が集まる×アテンション×キャンプファイヤー経営→
- →2021-05-04の日記×scrapboxのprivate→public転送について×面白さ×発見×気づき×自発的×知的生産×puppeteer×heroku×todo.txt×headless_chrome×研究×mvp×ブログ2.0×豆論文化×2021年4月の倉下アウトプット×キャンプファイヤー×2019年6月のアイデアライン×ゲーテッドコミュニティ×ウォールドガーデンモデル×ゲーテッドコンテンツ×組織×衰退×排除×scrapbox×yujiosaka×1×2×承認欲求の刺激につながる機能を全て排除する×はてなダイアリー×dotenv×envify×browserify×secure×httponly×requests×324×違いに気づく→
- →ネットワーク形成システムとしての未踏×人的ネットワーク×インフォーマル組織×パラレルワーク×観察者を置くことによる囚人のジレンマの破壊×互恵的×利己的×離脱・発言・忠誠×囚人のジレンマに耐性のあるコミュニティ構造×コミュニティによる生産性向上のすすめ×組織境界の曖昧化×二重組織×紹介者責任制→
- →まだらな未来が拡大しない×2hopリンク×津波てんでんこ×余裕があれば天球を支える×事後的に文脈がつながって大きなストーリーになる×connecting_the_dots×地球規模の熟議×日本文化ai×複数の視点に支えられたアイデアの理解コストは高い×良いアイデアなら許可を求めるな×結果が出てから評価する方が楽×日記2023-06-26×日記2023-06-28×日記2023-03-19×日記2022-06-27→
- →チームプレー×スタンドプレー×チームワーク×攻殻機動隊×個々人×自発的×事後的×スタンドプレーから生じるチームワーク×良いアイデアなら許可を求めるな×connecting_the_dots×点は事後的につながる→
- →新大陸×移住×社会制度×危険な場所×危険×詐欺師×新世界×移動×楽しさ×不安×魅力×新大陸が発見されたらどうするか×ゲートは隠すが柵の中の輝きは見せる×境界は一つではない×二重組織と正統的周辺参加→
- →エンジニアのための自分経営戦略×大衆を喜ばせるのは悪×知識と資本論とテクノロジストの条件×和で評価するとジェネラリストが選ばれる×属人性の排除には二種類ある×属人性×コンピュータグラフィクス、メディアアート、茶文化、そして、禅。×やる気のなくなるコメントの対処法×その技術を使わない方がいい×落合陽一の呪い×新概念の伝播×理解者になるためには×ものを作らない人は好き嫌いで定義され、好き嫌いは世界を狭くする×equality_v.s._equity×scrapboxベストプラクティス×ロジスティック回帰は回帰か分類か×nocodeと負の遺産×研究者の評価に数値基準を設けてはいけない×タユピンコ人のたとえ×限界費用逓増の法則が実感に合わない×svmで確率推定×「ちゃんとやれ」はミッドコアの思想×心理的安全な組織しか知らない人は、心理的安全性を理解するのが難しい×ワインに汚水を注ぐたとえ×盲点カード×わからないことに対する恐怖とその免疫×良いアイデアなら許可を求めるな×誰でもできるように、は過剰品質×positional_encoding×will/can/mustとアジャイル×無責任感×np.dot,_np.tensordot,_np.matmulの違い×「名前的型システムと構造的型システムの違い」加筆案→
- →やる気×ダニエル・ピンク×モチベーション×モチベーション1.0×生存欲求×モチベーション2.0×報酬×タイプx×モチベーション3.0×内発的動機×タイプi×自律性×autonomy×熟達×martery×ゴルディロックス×自己目的的×フロー×退屈×不安×目的×交換条件付きの報酬は自律性を失わせる×達成報酬×機能的固着の克服×measure_what_matters→
- →デザイン思考×tim_brown×組織×イノベーション×組織変革×邦題が変×予期せぬ発見の探索プロセス×制約×既存ビジネスとの適合を考えると平凡になる×良いアイデアなら許可を求めるな×大企業病×セクショナリズム×デザイン思考の本質は思考の具体化×エンジニアの知的生産術_加筆案×綜合×インテグレーティブシンキング×リスク許容度×無駄×生産性×漸進主義という負のスパイラル×楽観主義×steve_jobs×ブレインストーミング×ポストイット×収束→
- →タスク×ふせん×川喜田二郎×フェーズ×知識×あなた×サイクル×読み方×メタファ×本章×優先順位付け×kj法×全体像×しくみ×抽象化×プログラミング×やる気×ピラミッド×ソフトウェア×注×プログラム×whole_mind_system×パターン×プログラミング言語×ボトムアップ×たとえ話×価値×プロセス×知的生産術×分野×概念×アウトプット×グループ×学び×目的×他人×言語化×海馬×情報×考え方×誰か×視点×創造性×書き出し法×速度×盲点×教科書×原動力×方法×アナロジー×表札×発想法×方法論×それ自体×抜き書き×incremental_reading×単語×抽象概念×情報収集×見積り×一覧性×著者×文章×意思決定×シナプス×脳内×インプット×記憶×ルール×暗黙知×ゴール×写経×ソースコード×モデル×仮説×顧客×コンピュータ×実験×エンジニア×グラデーション×モデル化×アジャイル×supermemo×速読術×言葉×自分×複数×ボトルネック×ラット×複数人×フィードバック×具体例×symbolic_modelling×書籍×何回か×コーディング×岩波書店×メリット×レポート→
- →知的生産術×知的生産×サイボウズ×京都大学サマーデザインスクール×首都大学東京×川喜田_二郎×発想法×コーディングを支える技術×kj法×比較×目的×目的に注目×エンジニアの知的生産術_著者公式ページ→
"Engineer's way of creating knowledge" the English version of my book is now available on [Engineer's way of creating knowledge]

(C)NISHIO Hirokazu / Converted from [Scrapbox] at [Edit]